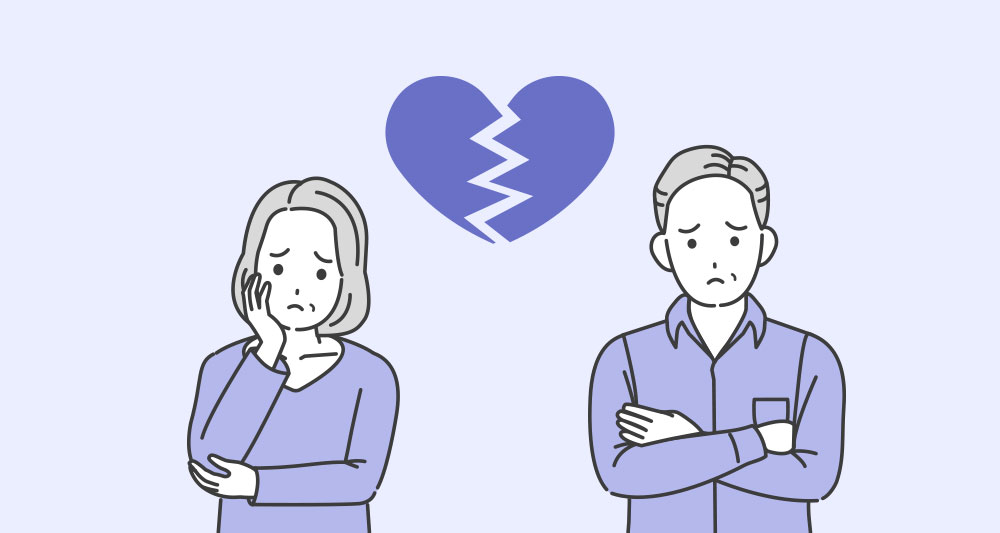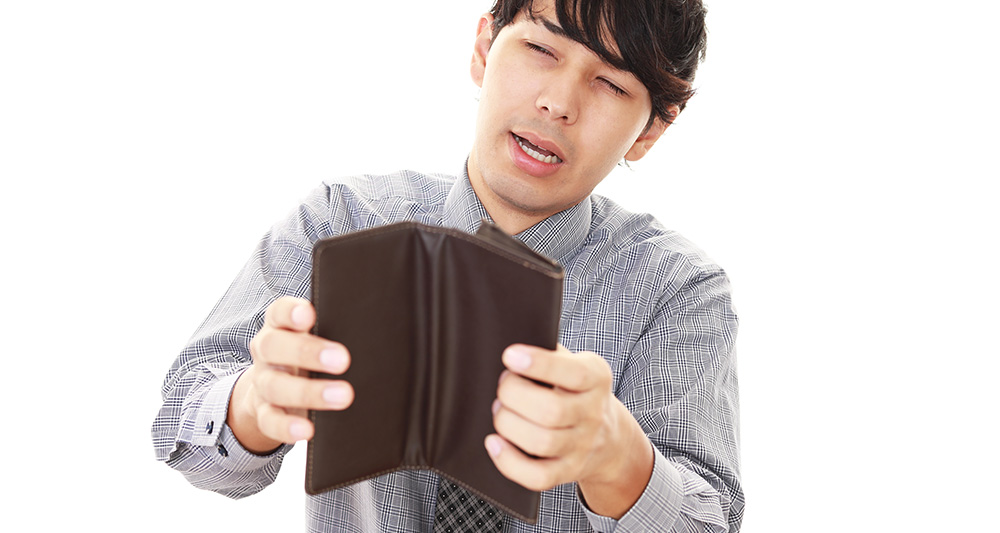離婚後の生活を支える年金分割とは?手続きの流れや必要書類を解説
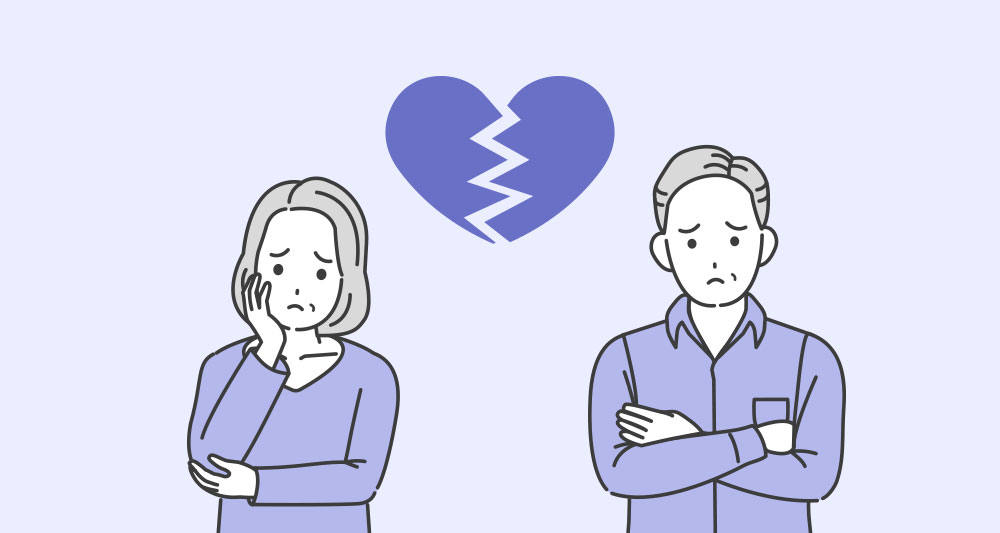
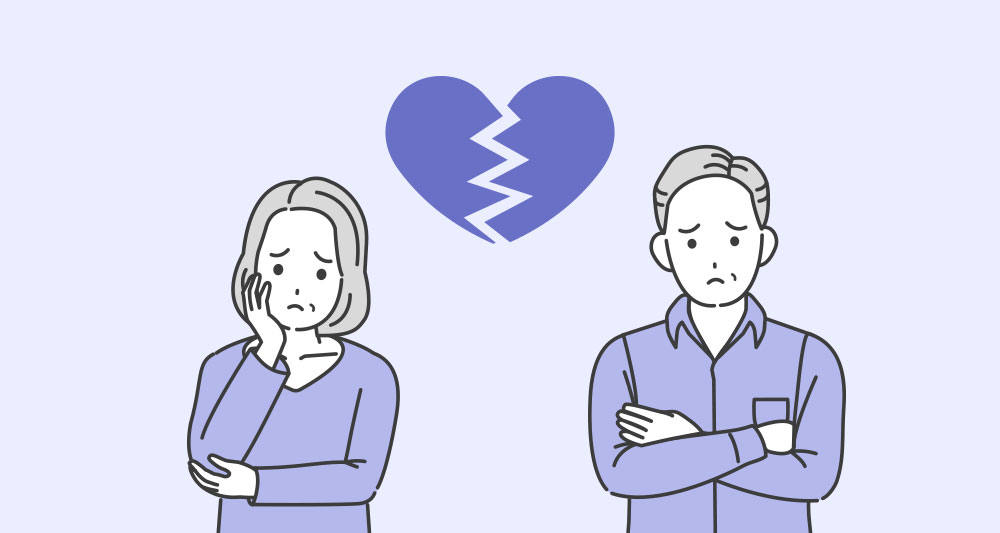
気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
【この記事を読んでわかること】
- 年金分割は離婚時に夫婦の厚生年金の納付記録をわけ合う制度
- 年金分割には夫婦の合意が必要な「合意分割」と合意不要の「3号分割」があり、年金記録を分割できる期間が違う
- 年金分割の請求期限は、原則離婚した日の翌日から2年以内(2026年6月の年金制度改正法後は5年以内に延長予定)。期限を過ぎると年金分割できなくなるので注意
離婚するかどうか悩んでいるとき、多くの人が気にかかるのは「離婚後の生活費や老後の暮らしは大丈夫なのだろうか」という点です。離婚した時には、それまで夫婦で築いてきた資産をどうわけ合うか話し合います。年金もわけ合う資産の1つであり、離婚した時には「年金分割」という制度で年金記録をわけることができます。今回は、年金分割の制度や手続き、年金分割でどのぐらい年金が変わるかなどを紹介します。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある
年金分割とは、離婚時に夫婦の厚生年金の納付記録をわけ合う制度です。
たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚したとします(夫と妻が逆でも同様ですが、以下は便宜上この設定で話を進めます)。離婚後、妻は老後に国民年金しかもらえないとなると、妻の生活が苦しくなります。
そこで、妻は夫の厚生年金の納付記録を妻にわけてもらうことで、妻自身の年金額を増やすことができます。これまで夫婦共同で生活していたのに、離婚すると年金に格差が生まれるのは不公平ということで、年金分割の制度が生まれました。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
<合意分割と3号分割>
- この表は横にスクロールできます
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 制度開始日 | 2007年(平成19年)4月1日 | 2008年(平成20年)4月1日 |
| 対象期間 | 婚姻期間全体 | 2008年(平成20年)4月1日以降の 婚姻期間で、第3号被保険者だった期間 |
| 夫婦の合意 | 必要 | 不要 |
| 分割割合 | 自由 (最大で保険料納付記録の2分の1) |
保険料納付記録の2分の1 |
| 請求期限 | 離婚日の翌日から2年以内 ※2026年5月までの民法改正に伴い「5年以内」に改正予定 |
|
(株)Money&You作成
合意分割は、年金を夫婦の合意によって分割する制度です。合意分割をすると、婚姻期間中の厚生年金の記録の最大2分の1(50%)にあたる部分をわけることができます。分割の割合は年金記録の少ない側(わけてもらう側)がもらえる上限が最大で2分の1と決められています。とはいえ、実際にはお互いに2分の1ずつ分割するケースが多いようです。
3号分割は、第3号被保険者(専業主婦(夫))として扶養者(配偶者)に扶養されていた期間の厚生年金の記録の2分の1(50%)を分割できる制度です。3号分割は夫婦の合意がなくても利用できます。しかし3号分割で分割できるのは、3号分割の制度がはじまった2008年4月1日以降の記録のみとなっています。
年金分割の請求期限は現状、離婚日の翌日から2年以内となっていますが、2025年6月に成立した「年金制度改正法」には、年金分割の請求期限が「5年以内」に延長されることが盛り込まれています。これは、民法の改正(離婚後の財産分与請求権の期限が2年から5年に延長される)に合わせたものです。
本稿執筆時点ではまだ施行されていませんが、民法の改正施行(2026年5月までに行われる予定)に合わせて年金分割の請求期限も「5年」と延長になる予定です。
なお、年金分割は「厚生年金の納付記録」をわけ合う制度なので、国民年金の部分は分割できません。自営業・フリーランスなど、厚生年金に加入していない場合には年金分割はできませんので注意しましょう。
合意分割・3号分割で年金額はどのくらい増える?
合意分割・3号分割でどのくらい年金額が増えるのか簡単に試算してみましょう。
計算条件
- 夫…会社員
- 妻…専業主婦(第3号被保険者)
- 夫の平均標準報酬額…36万円(ボーナスなしと仮定)
- 婚姻期間…1995年4月〜2025年3月(30年間・360カ月)
厚生年金の金額は、標準報酬額に一定の「係数」をかけて計算されます。この係数は年金制度の改正によって変わるため、2003年3月までとそれ以降で異なります。計算式は以下のようになります。
2003年3月まで…平均標準報酬月額×0.007125×厚生年金の加入月数
2003年4月以降…平均標準報酬額×0.005481×厚生年金の加入月数
「平均標準報酬月額」はボーナスを含まない金額、「平均標準報酬額」はボーナスを含む金額です。この合計が厚生年金の金額になります。
夫の厚生年金の金額(婚姻中の30年間分)
- 婚姻期間中の厚生年金の加入月数
2003年3月まで…8年間(96カ月)
2003年4月以降…22年間(264カ月) - 厚生年金額
2003年3月まで…36万円×0.007125×96カ月=24万6,240円
2003年4月以降…36万円×0.005481×264カ月=52万914円
24万6,240円+52万914円=年76万7,154円(月約6万4,000円)
合意分割の場合(2分の1ずつ分割したと仮定)
分割対象期間…1995年4月〜2025年3月(30年間・360カ月)
夫の厚生年金の金額…年76万7,154円
妻に分割される厚生年金の金額…年76万7,154円÷2
=年38万3,577円(月約3万2,000円)
3号分割の場合
分割対象期間…2008年4月〜2025年3月(17年間・204カ月)
妻に分割される厚生年金の金額…36万円×0.005481×204カ月÷2
=年20万1,262円(月約1万7,000円)
この例で妻の年金は、合意分割なら月約3万2,000円、3号分割ならば月約1万7,000円ですので、合意分割の方が金額的には有利です。
ただ、合意分割には両者の合意が必要です。離婚する相手とのことですから、合意がまとまらないこともあるでしょう。その場合は家庭裁判所で調停や審判を行うこともできますが、結果として3号分割を選んだ方が手間も時間も費用もかからなかった、となってしまう可能性もあります。
3号分割の場合、2008年4月1日の制度開始前の記録は分割の対象外です。つまり、2008年4月1日以降に結婚した方が離婚する場合は、合意分割でも3号分割でも将来もらえる厚生年金額は同じになります。
年金分割の手続きの流れ・期限・必要書類について
離婚が成立した後で、年金分割の請求手続きを行います。年金分割の手続きは、次のような流れで行われます。
1.情報通知書の取得
情報通知書は、年金分割をするにあたって必要な「分割対象の期間」や「標準報酬月額」などの情報が書かれた書類です。年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出することでもらえます。提出後、およそ1週間〜1カ月程度で情報通知書を受取れます。
「年金分割のための情報提供請求書」の書式は日本年金機構「離婚時に年金分割をするとき」からダウンロードできます。
2.年金分割の割合について話し合う(合意分割のみ)
合意分割の場合は、情報通知書の情報をもとに、夫婦間で年金分割について話し合い、分割の割合を決めます。話し合いで合意できた場合は、その内容をまとめた「年金分割の合意書」を作成します。合意できなかった場合は、家庭裁判所で審判や調停を行い決めてもらうこともできます。
3.年金分割の請求手続き
合意分割の場合は合意後、3号分割の場合は情報通知書の取得後、年金事務所で年金分割の手続きを行います。年金分割の手続きには次の書類が必要です。
- 年金分割の割合を明らかにすることができる書類
(年金分割の合意書、調停調書・審判書など) - マイナンバーカードまたは年金手帳等
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
- 住民票等(事実婚の場合)
「年金分割の合意書」の書式は日本年金機構「離婚時に年金分割をするとき」からダウンロードできます。
4.標準報酬改定通知書の受取り
手続きが終わると、保険料の納付記録が改定されます。後日届く「標準報酬改定通知書」には、改定の結果が書かれていますので、確認しましょう。
たとえ金額が少額であっても、将来もらえる年金が増える可能性があるなら、年金分割をした方がよいでしょう。
年金分割の請求期限
年金分割の請求期限は、原則として離婚をした日の翌日から2年(年金制度改正法の施行後は5年)以内です。また離婚成立後に相手方が亡くなった場合、亡くなってから1カ月が経つと請求できなくなります。
特に合意分割の場合は夫婦(元夫婦)で一緒に年金事務所に行くか、合意を証明する書面を提出する必要があるので、早めに手続きしましょう。
年金分割を受けた側の年金は月額3万円増える?
年金分割をすることで年金が増やせれば、離婚後でも老後の収入が増え、生活がしやすくなる側面はあります。厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金分割を受ける側の年金額の月額平均(国民年金を含む)は、分割前が5万7,979円、分割後が9万1,081円ですので、3万3,000円ほど増えています。しかし、それでも月約9万円で生活していくことは困難でしょう。
≫関連リンク
60歳以降も厚生年金に加入して働くと、いくら年金が増えるのか
離婚してもしなくても、老後のお金は年金以外にも用意する必要があることに変わりはありません。老後のお金は、早いうちからiDeCoやNISAなどを活用して自分で用意しておくようにしましょう。
≫関連リンク
【新NISA】夫婦それぞれで始めるべき?メリットは?
- 本ページは2025年9月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。
オススメ

頼藤 太希
経済評論家・マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)
頼藤 太希のプロフィールを見る