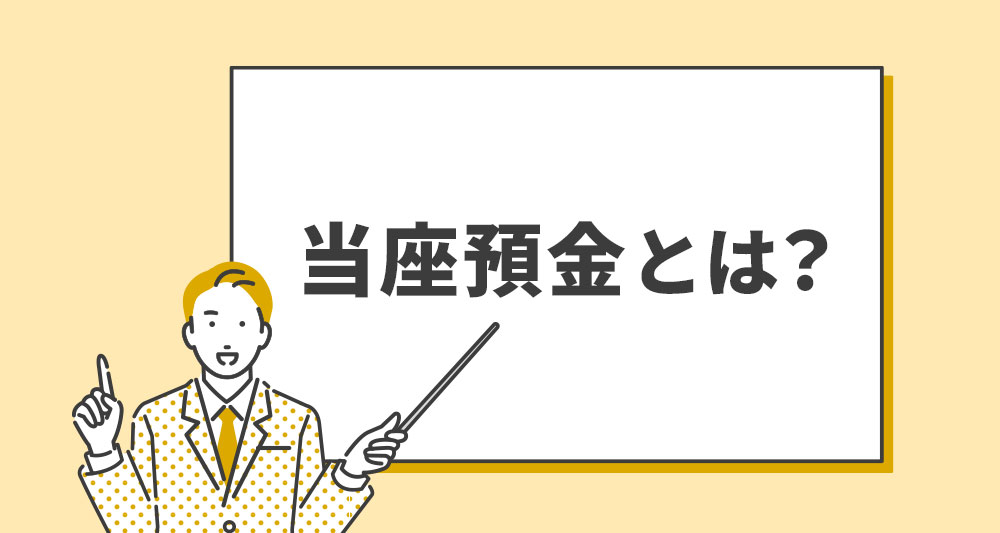
20代~60代それぞれでチェック!ライフステージごとの定期預金のかしこい活用法は?
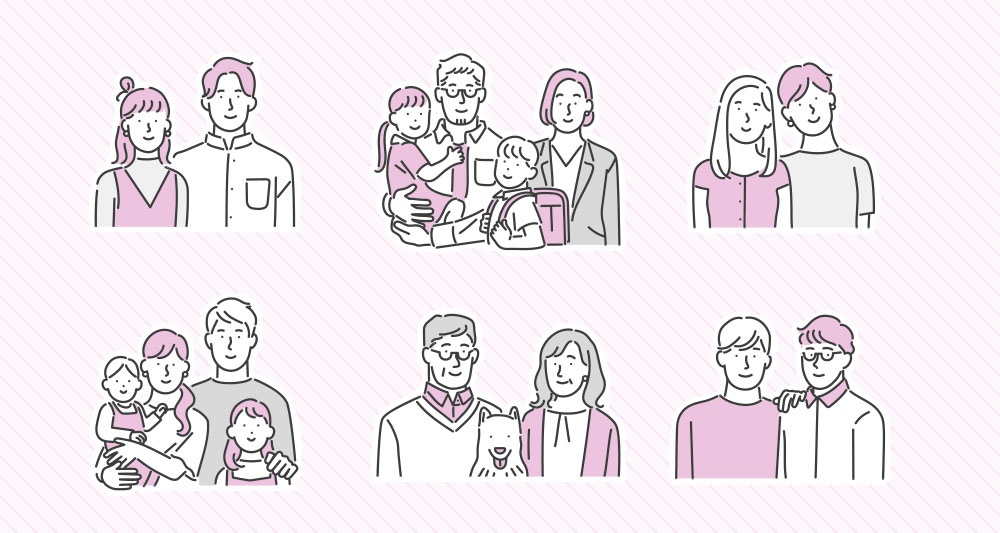
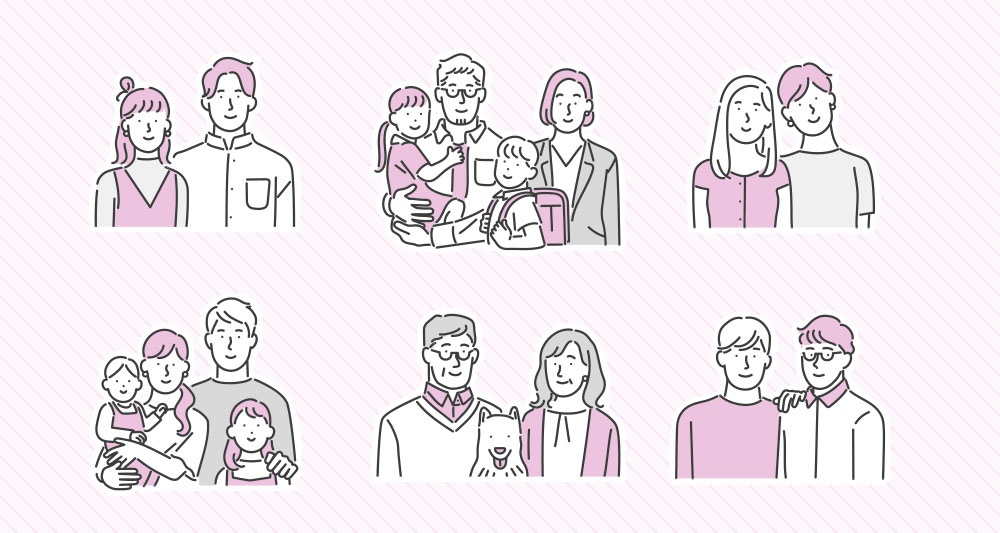
気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
私たちにとって定期預金は身近ですが、「なんとなくお金を預けている」という方もいるかもしれません。
自分のライフステージに合わせてマネープランを考え、定期預金を上手に利用することで、夢や目標をより実現しやすくなります。
そこで今回は、20代・30代・40代・50代・60代それぞれについて、ライフステージの特徴と、それに合わせた定期預金の上手な活用法についてご紹介します。
20代:「お金の基礎づくり」の時期
20代は多くの方が社会人となり、自分で収入を得てやりくりをはじめるスタートラインに立ちます。将来に向けて何をしたいかを考え、夢が広がっていく時期でもあります。
「いつ頃、何をしたいか」「何を買いたいか」といったライフプランを考えながら、それを実現するための「お金の基礎づくり」をはじめましょう。
また、急な病気やケガ、会社を辞めることになった場合などの緊急事態に備えて、生活費の3~6カ月分の「生活防衛資金」も準備していきましょう。
将来に向けての時間が長くあり、もし失敗してもリカバリーが可能な時期です。定期預金で安全性のある資金を増やしていきながら、リスクはあるが長期的なリターンが期待できる資産運用を一部取り入れてもよいでしょう。
20代の特徴
- 将来に向けてライフプランを考えよう
- 目標実現のために「お金の基礎づくり」をはじめよう
- 「生活防衛資金」として生活費の3~6カ月分を貯めよう
- リスクが多少取れる時期なので、資産運用も検討したい
20代の「定期預金の戦略」は?
20代では、普通預金にお金をすべて預けっぱなし、というケースもあります。「しばらく使わないお金」があれば、定期預金に預け替えましょう。
普通預金に比べて、定期預金は一般的に金利が高めなので、よりお金を増やすことが期待できます。ネット銀行は大手銀行よりも一般的に金利が高めですので、ぜひ利用したいところです。
また、毎月確実に預金を増やしていくために、毎月一定額を自動で貯める「積立式定期預金」もおすすめです。給与振込口座で設定すれば、毎月決まった日に決まった金額が定期預金に振替えられます。
銀行口座を1つだけにすると、システム障害やATMのメンテナンスなどによって利用できなくなる恐れがあるため、複数の銀行口座を持っておくと便利です。
その1つを「貯蓄専用口座」にすると、うっかり日常で使うことなく、貯蓄が確保されるのでおすすめです。
20代の定期預金活用法
- 生活費3~6カ月分の「生活防衛資金」を定期預金で貯めよう
- 金利が高めの銀行を利用しよう
- 自動積立定期預金で毎月コツコツ貯蓄を
- 「貯蓄専用口座」をつくるのもおすすめ
30代:「結婚・子育て」や「住まい」の準備期
30代は、結婚・出産を考える方も増えるでしょう。
結婚を考えはじめたら、パートナーと結婚に関するマネープランについて話し合いましょう。お金の話は、少しでも早い時期にはじめると話しやすい関係づくりができます。
出産の予定があれば、出産費用や出産後にかかる費用をチェックすることも大切です。どんな環境でどのように子育てをしたいかを、お金の面も含めて家族で話し合いましょう。
また、住宅を購入しようかどうか検討しはじめる方もいるでしょう。子どもがいる場合は、どのエリアで子育てをしたいかなど、教育環境なども含めてリサーチするとよいでしょう。
30代の特徴
- 結婚を考えはじめたら、2人で結婚関連費用の相談を
- 出産を控えたら、子育て費用も確認
- 住宅購入を考えていれば、早めにリサーチを
30代の「定期預金の戦略」は?
結婚が決まったら、結婚式や新居の費用を準備しましょう。二人で金額を決めて、コツコツ定期預金に貯めていくのもおすすめです。
妊娠したら、妊娠・出産時の費用や、その後の子育ての費用も貯めていきましょう。
子どもの教育費は、基本的には子どもが高校までは日々の家計から教育費を出し、大学以降の費用を、子どもが小さいうちから貯めていくプランがおすすめです。子ども名義の定期預金をつくるのもよいでしょう。
住宅を購入する場合は、頭金を準備しつつ、購入後に住宅ローン返済をどれくらいできそうかも試算しましょう。同じ金額の住宅を購入する場合、頭金を多く準備できれば、それだけ住宅ローン返済額を抑えることができます。
教育費や住宅購入費など、目的に合わせて銀行口座を使い分けると便利です。
30代の定期預金活用法
- 結婚を考えはじめたら、結婚費用の貯蓄を
- 出産後は、教育費の計画的な準備を。子ども名義の定期預金も手段のひとつ。
- 住宅購入を予定していれば、頭金の準備を
- 目的にあわせて、口座をつくると便利
40代:生活が安定し「さらなる成長」の時期
40代になると、ライフスタイルがある程度安定してきます。
家族と一緒に住むか、それとも1人で生きていくかなど、今後の予定も定まってきているでしょう。
働いている方は、キャリアのピークを迎えはじめる時期でもあります。今の仕事を続けるか、転職や異動をするかなど、今後のキャリアプランを考える方もいるでしょう。
今は長く働くことが一般的になってきたため、40代でさらなる成長を求めてキャリアアップ・収入アップを考える場合もあるかもしれません。それと同時に、何歳ぐらいに退職をするかのプランも立てはじめましょう。
子どもがいる方は教育費が多くかかる時期で、さらに住宅ローンも抱えていれば支出がかさむ時期ですが、がんばりどきです。
また、少し先の老後に向けて、老後資金を少しずつ準備していきたい時期です。
40代の特徴
- ライフスタイルがある程度固まる時期
- 長い現役時代を活かして、さらなるキャリアアップも
- 子育て家庭は教育費のピークが続く
- 老後資金の準備も少しずつはじめたい
40代の「定期預金の戦略」は?
40代は、子どもがいる方は、今後の子どもの教育資金について改めて確認しましょう。
進路の予定を話し合い、教育費が足りるかをチェックしましょう。教育費として定期預金の口座を別につくり、必要な資金を貯めていきましょう。教育費は多めに準備して、余ったら老後資金にまわすのも一案です。
マイホームがある方は、将来、水回りなどのリフォームの必要性が出てきます。その費用も定期預金で備えておきたいところです。
老後資金は、いざ退職してから「足りない」と焦ることのないように、現役時代にコツコツと貯めていきましょう。定期預金を利用するほか、老後まで時間がある40代なら、お金の一部をNISAやiDeCoなどの非課税制度を利用して資産運用をしていくこともよいでしょう。
40代の定期預金活用法
- 子どもの教育費をチェックし、子ども用の口座に別取りを
- マイホームがある人は、リフォーム費用も貯めておこう
- 老後資金もコツコツ貯めていこう
50代:「資産防衛とセカンドライフの準備」の時期
50代になると、そろそろ退職を意識し始める時期です。
今は退職をする年齢は、60歳から65歳など人それぞれです。65歳以降もさまざまな形で働き続ける方も増えています。今の仕事をいつまで続けるか、その後はどうするかを考えましょう。
定期収入を得られる時期はある程度限られるため、今ある資産はしっかり守っていきたいところです。さらに、老後資金の上乗せをしていきましょう。
そして、退職後のセカンドライフについてもじっくり考えていきましょう。どこに住んで、どんな生活をしていきたいでしょうか。具体的にイメージできれば、その準備が早めにはじめられます。
50代の特徴
- 退職時期をそろそろ考えてみよう
- 現在ある資産を、大切に守ろう
- 老後資金に向けて、コツコツ貯めていこう
- セカンドライフをイメージして準備を
50代の「定期預金の戦略」は?
50代になると、現役時代があと10年程度であるため、今後はリスクの高い金融商品は抑え、安全性の高い金融商品を選んでいくことが大切です。定期預金は元本割れのおそれがないため、心強いでしょう。
退職金を受取ったら、その資金をどうするかを具体的に考えておくことが大切です。退職金を元手に資産運用をはじめたい場合は、いきなりたくさんのお金をまわすことはリスクがあります。
まずは元本が保証された定期預金に預けておき、そこから少しずつトライしていきましょう。
定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
退職金は1,000万円を超える方も多いため、定期預金に預ける場合は1つの金融機関で1,000万円を超えないようにして、超える場合は複数の銀行に分けて預けましょう。
また、シニア向けに特別金利を設定している商品もあります。条件などもしっかり確認して、かしこく利用したいですね。
50代の定期預金活用法
- 老後資金として、定期預金も活用していこう
- 1つの金融機関の預金で1,000万円を超えないように、退職金は複数の金融機関に分けて預けよう
- シニア向け定期預金は中身をしっかりチェック
60代以降:「安心を得ながら、柔軟に過ごす」時期
60代以降になると、子どもがいる方も子どもが独立し、自分1人、もしくはパートナーと2人という生活になるケースが多い時期です。
また、一般的に65歳から年金を受取る方が多いです。年金は受取る時期を早めれば受取額が減り、受取る時期を遅くすれば受取額が増えるので、その試算をしてみてもよいでしょう。
65歳以降も働きつづけて収入が定期的にあれば、年金の受取りを遅らせて受取額を増やすという選択をする方もいます。
仕事を引退すると、月収やボーナスなどの大きな定期収入がなくなるため、年金などの収入と生活費とのバランスを考えましょう。支出の方が多ければ貯蓄を取り崩していくことになるため、貯蓄を取り崩してマイナスになることがないかを確認しておきます。
年齢を重ねると、病気やけがで入院することも増えるため、医療費や介護費の備えもはじめましょう。民間保険に加入している方は条件を改めてチェックし、何かあったときに活用できるように、忘れずに家族に伝えておくことも大切です。
仕事を引退したら、自由な時間が増える時期です。趣味に没頭したり旅行に行ったりと人生を長く楽しんでいくために、お金を計画的に準備し、使っていきたいところです。
60代以降の特徴
- マネープランを考え、年金の受取時期を検討
- 医療費や介護費を準備し、保険も含めてチェック
- 仕事を辞めた後の収支についても確認
- 趣味や旅行をおもいきり楽しめる時期
- お金が足りなくならないよう、計画的に使おう
60代以降の「定期預金の戦略」は?
60代以降では、生活資金を安定的に確保することが最優先になります。医療や介護が必要になった場合に備えて、ある程度まとまったお金を定期預金に預けておきましょう。
資産運用に回しているお金が多い方は、利益が出ているタイミングで少しずつ売却し、元本保証のある定期預金に預け替えていくことも大切です。
また、使わない銀行口座があれば解約して整理することも大切です。さまざまなATMで使えるネット銀行の口座を1つ用意しておくことも一案です。
将来的な相続のことについても確認しておきましょう。今ある資産について、さまざまな定期預金の残額などを確認しながらチェックします。相続税が発生する場合は、その対策もしておくといいでしょう。判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することも大切です。
60代の定期預金活用法
- 預金口座を確認し、使っていない口座は解約を
- さまざまなATMが使える銀行など、利用しやすいものの検討を
- 医療費や介護費も定期預金で備えておこう
- 相続については税理士など専門家に相談
ポイントは「柔軟性」と「目的」
ここまで解説してきたように、20代~60代のそれぞれのライフステージごとに、考えたいことや準備するお金は異なります。
今、そして今後どのように過ごしたいか、ライフプランを立てながら、それに合わせて必要な資金を準備していきましょう。
ある程度まとまった預金があれば、やりたいことが出てきた際にも、柔軟に対応ができます。
資産運用も大切な時代ですが、安全な資産形成ツールとして、定期預金もぜひ上手に活用したいところです。目的に合わせて複数の金融機関で口座を開き、それぞれ貯めていくとよいでしょう。
年1回、定期的なメンテナンスを
自分の夢や目標、まわりの環境はどんどん変わっていくものです。定期的にライフプランとマネープランを確認していきましょう。
年1回は、お金まわりの見直しをするのもおすすめです。年末や3月の年度末、自分の誕生日など、時期を決めておくと忘れません。自分の資産状況や今後のマネープランを確認して、夢や目標に合わせてお金を準備していきたいですね。
定期預金の金利も変化があるため、より高い金利の定期預金があれば、預け替えるのもよいでしょう。
10年以上先に使うお金であれば、例えばNISAやiDeCoなどの税制優遇制度も活用しながら、一部の資金を運用していくのもよいでしょう。わからないことがあれば、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも大切です。
- 本ページは2025年1月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
オススメ

西山 美紀
ファイナンシャルプランナー
出版社で編集・マーケティングに従事後、2005年にフリーライターとして独立し、FP資格を取得。貯蓄・節約・投資・保険といった、暮らしに身近なお金のテーマを中心に、子育てや生き方に関する取材・執筆・監修・講演等を行う。単に貯蓄額だけを増やすのではなく、うるおいのある毎日のためのお金の使い方・貯め方・増やし方を発信。著書に『お金が貯まる「体質」のつくり方』(すばる舎)、『お金の増やし方』(主婦の友社)等。男女2児の母。現在心理学を専攻する大学生でもあり、より心豊かに生きるヒントについて研究中。
西山 美紀のプロフィールを見る






