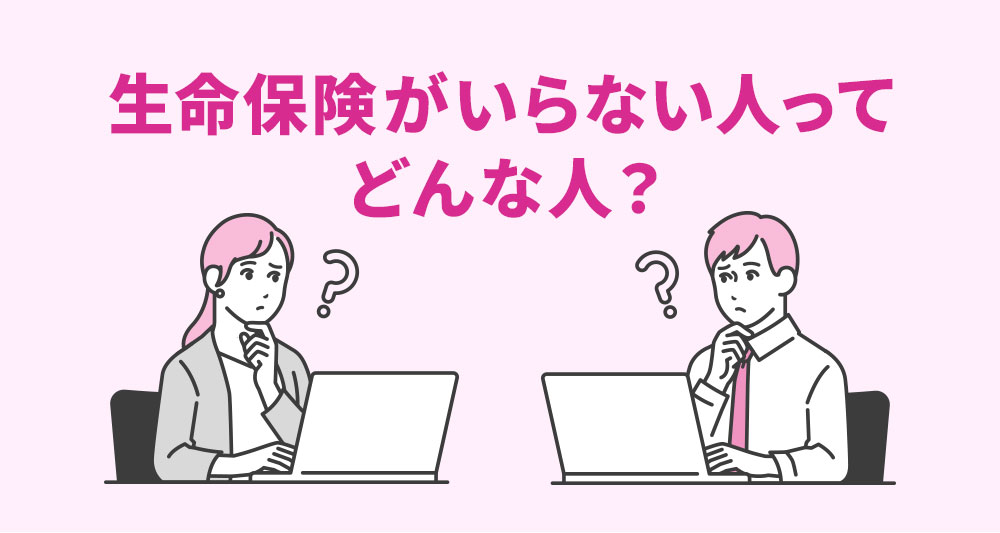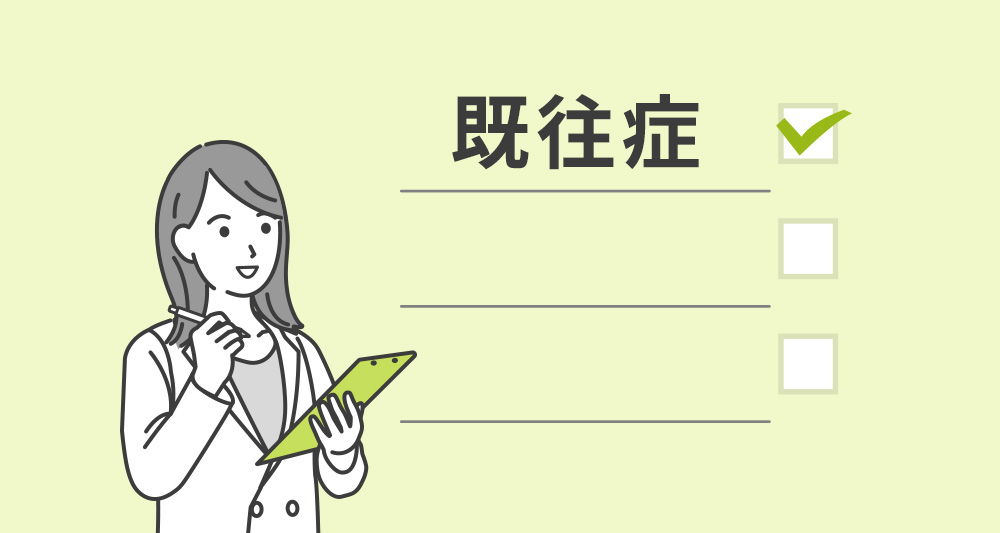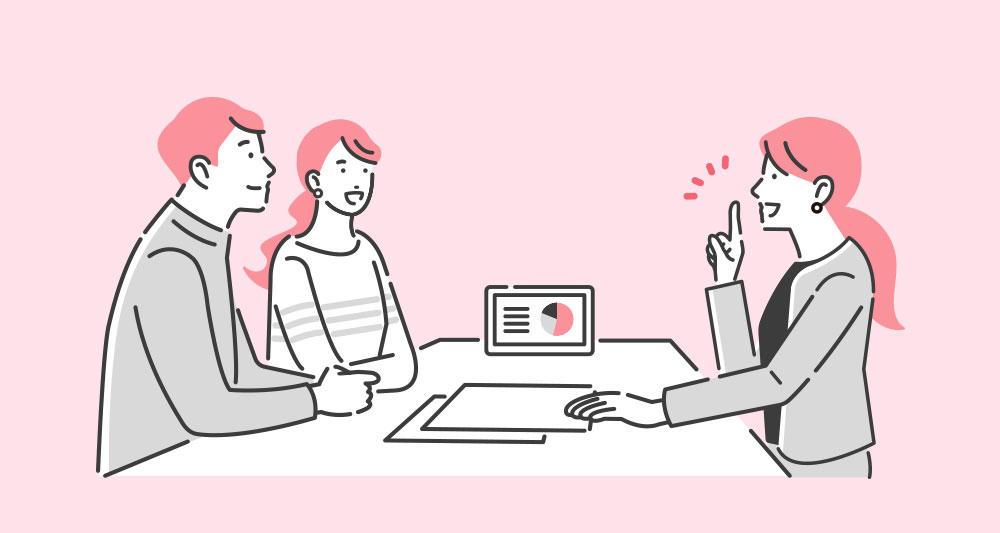<みんなの平均>生命保険は毎月いくらかける?年代別の平均保険料から選び方を解説


気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
生命保険は家族の安心を守る大切な備えですが、「毎月の保険料は適正なのか」「他の家庭と比べて保険料が高いのではないか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。本コラムでは、最新の調査結果による平均払込み額を紹介しつつ、保障内容の見直し方や保険料を抑えるポイントを解説します。無駄を省きながら必要な保障を確保するための参考にしてください。
生命保険で毎月払っている保険料はいくら?
毎月支払っている保険料の平均額を、公益財団法人 生命保険文化センターが公表している「生命保険に関する全国実態調査」(令和6年度)から確認してみたいと思います。
加入者全体の年間平均払込み額
「生命保険に関する全国実態調査」(令和6年度)によると、生命保険(個人年金保険を含む)に加入している世帯の平均年間払込み保険料(全生保)は、35万3,000円となっています。
なお、世帯の平均年間払込み保険料とは、保険料払込み期間中の契約について、1つの世帯が1年間に支払う保険料総額の平均額をさしています。
世帯主の年齢別の平均額
世帯ごとの平均年間保険料払込み額を世帯主の年齢別に見てみましょう。
下記の表では、40代を過ぎた頃から払込み保険料は上がり、55歳頃にピークを迎えている様子が見られます。これらの要因としては、死亡保障や医療保障は年齢が上がるにつれて保険料が高くなることのほか、子どものいる家庭では、死亡保険金額を高く設定することや学資保険に加入する傾向にあることも考えられます。
一方、年齢の若い層では年間払込み保険料が低くなる傾向があります。生命保険の保険料は年齢が低くなるほど安くなることが理由の1つでしょう。
- この表は横にスクロールできます
| 世帯主の年齢 | 世帯での年間払込み保険料 | 世帯での月額払込み保険料 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 32万2,000円 | 2万7,000円 |
| 30~34歳 | 29万8,000円 | 2万5,000円 |
| 35~39歳 | 31万2,000円 | 2万6,000円 |
| 40~44歳 | 37万4,000円 | 3万1,000円 |
| 45~49歳 | 36万8,000円 | 3万1,000円 |
| 50~54歳 | 38万2,000円 | 3万2,000円 |
| 55~59歳 | 40万7,000円 | 3万4,000円 |
| 60~64歳 | 34万3,000円 | 2万9,000円 |
| 65~69歳 | 35万4,000円 | 3万円 |
| 70~74歳 | 34万5,000円 | 2万9,000円 |
| 75~79歳 | 30万8,000円 | 2万6,000円 |
| 80~84歳 | 28万2,000円 | 2万4,000円 |
| 85~89歳 | 25万3,000円 | 2万1,000円 |
| 90歳以上 | 32万6,000円 | 2万7,000円 |
- 月額払込み保険料は、年間払込み保険料を12カ月で割り、1,000円未満を四捨五入した金額です。
公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 」(令和6年度)より
世帯年収別の保険料平均額
200~500万円未満層では、年間25万円前後でほぼ横ばいの状態となっています。それに対して、500万円を超えるあたりから一気に上昇し、年収が高いほど保険料も高くなる様子が見られます。
年収による払込み保険料の違いは、保障に対するニーズの違いによることが要因の1つかもしれません。たとえば年収200〜500万円未満層では、生活費自体が相対的に少なく、最低限の保障で済む傾向があります。一方で年収が高い世帯は、生活水準も高いことが多いため、万一の時に必要な保障額(遺族の生活費、教育費など)が大きくなることもあるからです。
他にも、家計の余裕度による違いも考えられます。たとえば年収200〜500万円未満層では、可処分所得が限られるため「必要最低限の保険」に留まることもあるはずです。収入に余裕がある層では、医療保険・がん保険・学資保険・個人年金などを追加し、払込み額が増えることもあるでしょう。
- この表は横にスクロールできます
| 世帯年収 | 世帯での年間払込み保険料 | 世帯での月額払込み保険料 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 25万2,000円 | 2万1,000円 |
| 200~300万円未満 | 24万4,000円 | 2万円 |
| 300~400万円未満 | 25万3,000円 | 2万1,000円 |
| 400~500万円未満 | 25万2,000円 | 2万1,000円 |
| 500~600万円未満 | 32万2,000円 | 2万7,000円 |
| 600~700万円未満 | 33万5,000円 | 2万8,000円 |
| 700~1,000万円未満 | 39万9,000円 | 3万3,000円 |
| 1,000万円以上 | 55万4,000円 | 4万6,000円 |
- 月額払込み保険料は、年間払込み保険料を12カ月で割り、1,000円未満を四捨五入した金額です。
公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 」(令和6年度)より
家族構成別の年間保険料平均額
年間保険料平均額は、家族構成によって異なることが分かります。
教育費のピーク期(高校〜大学生の子どものいる世帯)で保険料が最も高くなる傾向があります。子どもの教育費や親の死亡保障に備える保険に加入していることが多いからでしょう。対して子どもが小さい時期は保険料を抑える傾向があることが分かります。
- この表は横にスクロールできます
| 家族構成 | 世帯での年間払込み保険料 | 世帯での月額払込み保険料 |
|---|---|---|
| 夫婦のみ(40歳未満) | 44万3,000円 | 3万7,000円 |
| 夫婦のみ(40~59歳) | 32万1,000円 | 2万7,000円 |
| 末子乳児 | 24万7,000円 | 2万1,000円 |
| 末子保育園児・幼稚園児 | 36万円 | 3万円 |
| 末子小・中学生 | 37万6,000円 | 3万1,000円 |
| 末子高校・短大・大学生 | 40万2,000円 | 3万4,000円 |
| 末子就学終了 | 37万4,000円 | 3万1,000円 |
| 高齢夫婦 有職(60歳以上) |
36万7,000円 | 3万1,000円 |
| 高齢夫婦 無職(60歳以上) |
24万6,000円 | 2万1,000円 |
- 月額払込み保険料は、年間払込み保険料を12カ月で割り、1,000円未満を四捨五入した金額です。
公益財団法人 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査 」(令和6年度)より
生命保険の選び方、見直し方
生命保険は加入したら終わりではありません。その時々の状況に応じて見直すことで、必要な保障を備えながら保険料の削減につながることもあります。そこで生命保険の選び方と見直し方のポイントを確認してみましょう。
必要な保障を軸に考える
必要な保障は、家族構成や年代によって異なるものです。現在何の保障が必要かを軸に考える必要があります。そのために、今「何の保険に加入しているか」を洗い出してみて、一覧表にしておくことをおすすめします。もし保障に過不足があるようでしたら、追加や削減を考えましょう。
さらに「必要保障額」を算出することも大切なアクションです。必要保障額は、万一のときに家族に必要なお金(生活費・教育費・住宅費)から、公的保障(遺族年金など)や貯蓄を差引いて計算すると算出できます。
必要保障額=(遺族の生活費+教育費+住宅費など)-(公的保障+貯蓄・資産・収入+児童手当など)
なお、必要保障額はイオン銀行のライフプランシミュレーションを使って計算することも可能です。活用してみてはいかがでしょうか。
加入中の保険の保障と必要保障額が分かったら、具体的な商品を検討します。その際、保険料の安さだけに着目してしまうと、備えるべき保障を確保できなくなる可能性があります。あくまで必要な保障を軸に考え、保険商品を選びましょう。
≫関連コラム
保険って何?仕組みや種類など基礎知識を簡単に解説
ライフステージに応じて見直す
保険は就職や結婚、子どもが生まれるなどのライフステージの変化で加入すべき保険や備える保障が変わってきます。以下は、保険の見直しに最適な代表的なタイミングです。ぜひ覚えておきましょう。
保険の見直しに適した代表的なタイミング
- 就職
- 結婚
- 子どもの誕生
- 子どもの進学
- 住宅を購入した時
- 子どもの独立
- 定年退職
≫関連コラム
生命保険の見直しのポイント!年代別の必要な保険をご紹介
生命保険の保険料を抑えるには
保険の保険料を抑えるには、まず自分が加入している保険を一覧表に書き出し、ライフステージに合わせて見直すのがおすすめです。見直しのポイントを整理してみましょう。
必要な保障内容を軸に見直す
万一の死亡保障額が大きすぎたり、医療保障が重複したりしている場合は、保険の見直しにより保険料の削減が期待できます。また、独身時代と子育て期、定年後では必要な保障が変わるものです。状況に合わせて見直すことで、必要な保障が確保できる上に、余分な保障を解約すれば保険料も抑えられます。
一方、公的な保障を考慮することも、保険料を抑えるために有効です。なぜなら公的な「遺族年金」や「高額療養費制度」などを考慮することで、おのずと民間保険でカバーすべき範囲を絞ることができるからです。
保障期間を見直す
保障期間は長期的に見るとトータルコストに差が出るので、保障が本当に必要な年齢を見極めることがポイントです。たとえば、一生涯保障(終身型)より定期型を選ぶと、期間限定となるため保険料は安く抑えられるでしょう。また、子どもが独立するまでの期間だけ大きな保障を付け、その後は縮小させるといったように、必要な時期に合わせて保険に加入することも保険料を抑えるには効果的です。
掛け捨て型にする
掛け捨て型の保険は、保険料が割安で大きな保障が得られることがメリットです。万一の際に大きな保障額を確保したい方に適しています。
一方、貯蓄型(終身保険・養老保険)は、保険料は高めになりますが、解約返戻金や満期金があります。長期の資産形成や相続対策にメリットのある保険です。
それぞれの特徴を踏まえ、「大きな保障が必要な時期は掛け捨て型保険で資産形成をする」「老後資金や余裕資金は貯蓄型保険で資産形成をする」といったように組み合わせるのも一案です。
≫関連コラム
掛け捨て型保険or貯蓄型保険 あなたに合う選び方は?
まとめ
生命保険の世帯での平均年間払込額は35万3,000円で、年齢が上がるほど高くなり55歳前後でピークを迎えます。年収や家族構成によっても差があり、高収入層や子育て世帯は払込み額が高めな傾向があります。保険料削減には、保障内容や期間の見直しのほか、公的保障を踏まえて調整することや、掛け捨て型と貯蓄型保険の使い分けが有効です。
もっと詳しく話を聞きたい方は、お気軽にイオン銀行で無料相談・来店予約をしてください。
- 本ページは2025年9月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性など内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。
オススメ

小沢 美奈子
ファイナンシャルプランナー
マネーライター。
家計および投資初心者の相談に実績あり。
大学卒業後、損害保険会社にて社員教育、研修講師などを経験。約12年間勤務後、外資系損害保険会社で営業に従事。会社員時代に取得したファイナンシャルプランナー資格を活かし2015年に事務所「KandBプランニング」を開業。
雑誌やWebのマネー記事執筆、セミナー講師、家計相談のほか、写真撮影も行う。趣味はカメラとバレエ。著著「本物の節約・残念な節約」(河出書房新社)