
「米国株は割高でリスクが高い」という問いへの僕なりの答え
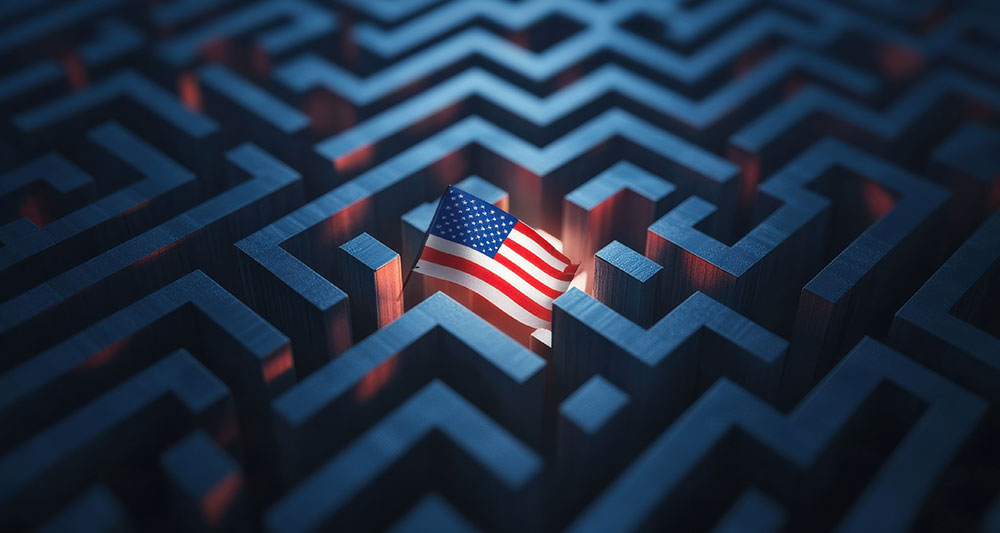
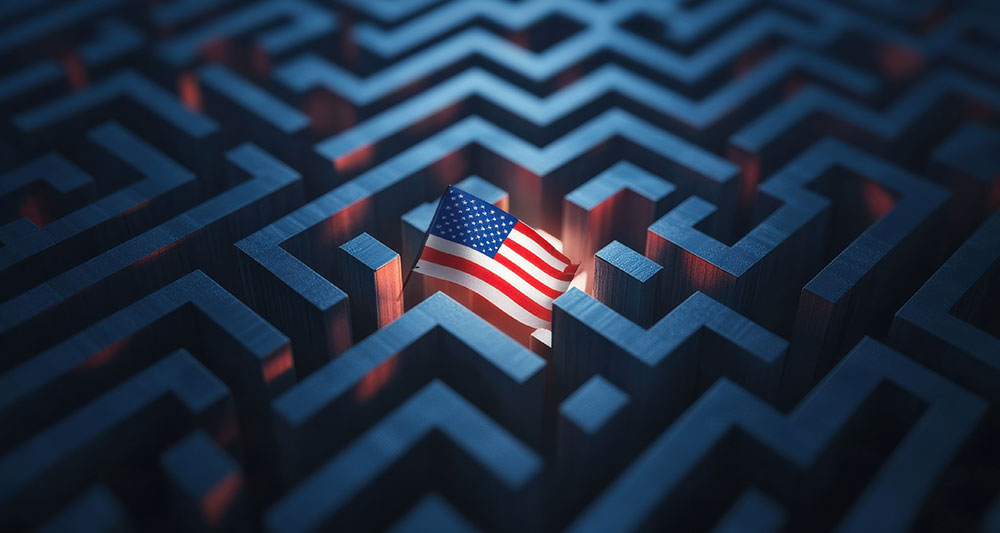
気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
僕の仕事としての米国株との付き合いは、1987年に始まりました。そこから37年の間、文字通り山あり谷ありのマーケットの変動を見てきたことになります。
社会人1年目1987年の10月には、マーケットを揺るがす歴史的大事件「ブラックマンデー」が起こりました。この日ニューヨーク・ダウが一日で22%も下落したのです。
当時の僕は、ウォール街にある米系証券会社で働き始めたばかりの新人社員。暴落の余波で、周囲のアメリカ人の先輩たちが次々と業績悪化によって解雇されていく姿を目の当たりにしました。
入社わずか1年目にして、自分もこのまま職を失うのではないか――そう真剣に悩んだのを、今でも鮮明に覚えています。
その後、米国株は時間をかけて立ち直り上昇を継続しましたが、2000年代に入ると再び大きな試練が訪れます。ITバブルの崩壊です。ナスダック銘柄を中心に大きく株価は暴落したのです。その回復を待たずして今度は2008年、「リーマン・ショック(世界金融危機)」がマーケットを直撃しました。株式市場は再び奈落へと沈みました。しかし、驚くべきことにその後の米国株の回復力は目を見張るものがありました。
世界で最も早く、金融危機前の高値を更新し、そこからの上昇を続けていったのです。
その後も新型コロナ、トランプ関税などによる暴落をしたものの、その後は急激にリバウンドし、ついに先週もS&P500は史上最高値を更新しました。
そんな米国株について、「米国株のマーケットは割高であり、米国株投資はリスクだ」と言う意見を散見するようになりました。
実は、これは面白いことに、ここ十数年間で僕が日本の個人投資家のみなさんに米国株の魅力について話すたび、ほぼ必ずと言っていいほど受けるコメントでもあるのです。
ただ、事実はというと、そのような見方があり一時的に株価の下げがあったとしても、米国株は上昇を続けてきたのです。ですから、これまでのところ、もっともらしく聞こえる米国株否定論はことごとく間違ってきたのです。
アメリカの企業には、バリュエーションだけでは説明できない、日本企業と違ういくつかの際立った強みがあることを忘れてはなりません。
第一に、世界中の消費者を惹きつけるマーケティングの巧みさ。グローバル市場においてブランドを構築し、訴求力を最大化する技術は、他国の企業を大きく凌駕しています。
第二に、業績が悪化した際には、感情に流されることなく、冷静かつ迅速に人員削減や事業再編を断行できる「柔軟性(フレキシビリティ)」。これは、経営判断のスピードと質に直結する、非常に大きな構造的利点です。
第三に、「まずやってみよう」「失敗したら直せばいい」という、試行と修正を前提とした合理的で実践的な企業文化。こうした文化が、現場レベルでのイノベーションを後押しし、新たな成長機会を次々に生み出しています。
こういった米国企業の構造に気づかず、短期的な株価のバリュエーションや政治情勢に気を取られていると、気づけば市場の上昇から取り残され、機会損失をだしてしまう──僕は、そちらの方が大きなリスクだと思っています。
本コンテンツは情報提供を目的としており、商品申込等の勧誘目的で作成したものではありません。本情報はマネックス証券株式会社が作成したものとなり、株式会社イオン銀行(以下、当行)はその情報の正確性や完全性を保証するものではありません。本情報を使用することにより生ずるいかなる種類の損失について、当行は責任を負いません。なお、コンテンツの内容は、予告なしに変更することがあります。
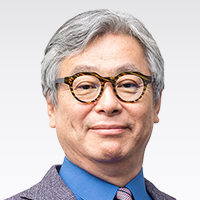
岡元 兵八郎
マネックス証券 チーフ・外国株コンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー
上智大学卒業後、ソロモン・ブラザーズ証券(現シティグループ証券)に入社。東京・ニューヨーク勤務を含め26年間、外国株式関連業務に従事。上級管理職として機関投資家向けにグローバル株式投資の拡大を推進し、世界54カ国の市場への投資を支援。SMBC日興証券では米国株の分析・資料作成を担当し、個人投資家向けにも情報を発信。北米滞在10年、訪問国80超、33カ国以上の証券取引所・企業訪問の経験を持つ。2019年より現職。著書に『日本人が知らない海外投資の儲け方』、『本当に資産を増やす米国株投資』など。
岡元 兵八郎のプロフィールを見る

