
【米国株】バフェット効果でNYダウもついに史上最高値を更新、利下げ期待が後押し


気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
主要指数がそろって史上最高値を更新、ユナイテッドヘルス・グループ[UNH]の急伸も寄与
先週(8月11日週)の米国株式市場は、投資家心理の強気と慎重さが交錯するなかで、主要指数がそろって史上最高値を更新しました。S&P500は0.94%上昇し、ナスダック100も0.43%高で1週間を終えました。ダウ平均も金曜日(8月15日)にはユナイテッドヘルス・グループ[UNH]の急伸が寄与し、ざら場中に初めて45,000ドルを突破しました。
背景には、インフレの沈静化を示す米消費者物価指数(CPI)の結果がありました。7月CPI(前年比)は+2.7%と市場予想(+2.8%)を下回り、6月の+2.7%から横ばい。これにより9月会合での利下げ観測が強まりました。一方で、生産者物価指数(PPI)前年比は市場予想を上回る+3.3%と上振れし、関税や輸送コストが企業収益を圧迫しつつある懸念を残しました。結果として「インフレ横ばい」という安心感と「コスト高再燃」という警戒感が拮抗し、指数は高値圏で神経質に推移しました。
CPI発表後は利下げ期待がマーケットを後押ししました。週末時点では、次回FOMC(連邦公開市場委員会)で0.25%の利下げが実施されるとの見方が優勢となっています。こうした環境下、小型株指数ラッセル2000は先週3%上昇し、大型株を上回るリターンを記録しました。背景には、小型株が相対的に高い負債比率を抱えているため、金利低下による資金調達コストの軽減効果をより直接的に享受しやすいという構造的要因があります。
「バフェット銘柄」がダウ平均を高値へ導く、S&P500ヘルスケアセクタ指数は週間で4.6%上昇
セクター別の騰落では、ヘルスケアが圧倒的な勝者となりました。ユナイテッドヘルス・グループは先週21%高、ダウ平均を日中最高値更新へと導いたためです。これはバークシャー・ハサウェイ[BRK.B]が第2四半期に160億ドル超のユナイテッドヘルス・グループ株を新規取得していたことが判明し、「バフェット銘柄」としての信認が株価を押し上げました。
長期的な視点で投資をするバフェット氏は、ユナイテッドヘルス・グループの問題は短期的なものと解釈、司法省による調査や請求問題はあるが、売られ過ぎた局面では投資妙味があると判断したようです。同社のキャッシュフローは250億ドル規模であり、バリュエーション的にも過去20年で最も割安なレベルにあります。今回のバフェット氏の同社株の買いがきっかけで、2025年に入り大きく下落していたS&P500ヘルスケアセクタ指数は週間で4.6%の上昇となりました。ユナイテッドヘルス・グループ一社だけで2025年ダウ指数を1,000ドル以上押し下げています。
バークシャーのユナイテッドヘルス・グループ買いの一方、アップル[AAPL]とバンク・オブ・アメリカ[BAC]は、バークシャーが保有株を一部売却したとの報道で軟調に推移。市場は「選別」を進めるバフェットの動きに敏感に反応しました。
半導体関連ではアプライド・マテリアルズ[AMAT]が決算を嫌気して二桁の下げとなり、テクノロジー株の上昇に水を差す格好となりました。対照的にユナイテッド・エアライン・ホールディングス[UAL]は決算が市場予想を上回り、旅行需要の底堅さを背景に株価が急伸しました。インフレ環境下でも消費者が体験型支出を重視していることが示され、航空・観光関連銘柄には追い風が吹きました。
パウエルFRB議長のジャクソンホール講演を控えて「期待と警戒の綱引き」
市場が次に注目しているのは、現地8月22日に予定されるジャクソンホールでのパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演です。現在、先物市場では9月FOMCでの0.25%利下げを90%以上織り込んでいます。しかし、PPIや小売売上高など一部の指標が強含んでいることから、利下げ幅やペースに関しては確実性が高いとは言えません。
パウエル議長は「データ依存」を繰り返す可能性が高く、市場の過度な利下げ期待を抑制する可能性があります。投資家にとっては、短期的な金利の道筋以上に、FRBが中期的にどの程度インフレリスクを重視しているかが重要なポイントになります。
今週(8月18日週)は小売セクターに焦点が集まります。ウォルマート[WMT]、ホームデポ[HD]、ターゲット[TGT]の決算は、米国消費の底堅さを測る試金石となります。先週は市場内部で資金のローテーションが進み、出遅れ株への物色と過熱気味銘柄の冷却が並行して進みました。これは基調としてプラスですが、今後の市場動向は小売決算とパウエル議長の発言に大きく左右される公算が大きいでしょう。加えて、今週の住宅市場データや8月PMI速報も景気認識を左右する重要指標であり、予想との乖離が大きければ市場のボラティリティを高める要因となります。
トランプ・プーチン会談が実現、株式市場における政治的不確実性を減らす可能性も
先週金曜日8月15日(米国時間)、アラスカの米軍基地において、トランプ米大統領とプーチン露大統領の首脳会談が行われました。両首脳が握手を交わした瞬間、米軍機がB2爆撃機を中心に編隊を組み、戦闘機がその護衛として低空飛行を行いました。これは米国が自らの圧倒的な軍事力を誇示し、交渉の場における優位性を暗黙に示す演出であったことは間違いありません。
会談の成果については、ホワイトハウスが事前に意図的に期待値を低く設定していました。トランプ米大統領は今回を「探り合いの会談」と表現し、ホワイトハウスも「傾聴のための演出」と説明しています。つまり、具体的な合意形成よりも、相手の立場や意図を見極めることに主眼が置かれていたと言えます。
両首脳の目標は根本的に異なります。トランプ米大統領が「和平」を目指している一方で、プーチン露大統領は「勝利」を求めています。さらに両者はいずれも交渉において「敗北」を受け入れる性格ではなく、譲歩の余地が限られている点が、将来的な合意形成を難しくしています。
しかしながら、この会談自体は大きなマイルストーンとなります。たとえ具体的な成果が乏しかったとしても、対話の枠組みが動き出したことは事実であり、今後の展開次第では、3年半に及ぶロシアによるウクライナ侵攻による地政学的リスク、つまり株式市場における政治的不確実性を減らす可能性があります。
次の展開としては、米国時間の月曜日8月18日に、ウクライナのゼレンスキー大統領や欧州の首脳たちがホワイトハウスを訪問し、トランプ米大統領と会談する予定です。
本コンテンツは情報提供を目的としており、商品申込等の勧誘目的で作成したものではありません。本情報はマネックス証券株式会社が作成したものとなり、株式会社イオン銀行(以下、当行)はその情報の正確性や完全性を保証するものではありません。本情報を使用することにより生ずるいかなる種類の損失について、当行は責任を負いません。なお、コンテンツの内容は、予告なしに変更することがあります。
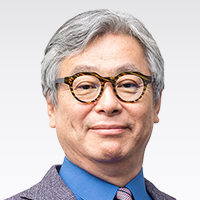
岡元 兵八郎
マネックス証券 チーフ・外国株コンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー
上智大学卒業後、ソロモン・ブラザーズ証券(現シティグループ証券)に入社。東京・ニューヨーク勤務を含め26年間、外国株式関連業務に従事。上級管理職として機関投資家向けにグローバル株式投資の拡大を推進し、世界54カ国の市場への投資を支援。SMBC日興証券では米国株の分析・資料作成を担当し、個人投資家向けにも情報を発信。北米滞在10年、訪問国80超、33カ国以上の証券取引所・企業訪問の経験を持つ。2019年より現職。著書に『日本人が知らない海外投資の儲け方』、『本当に資産を増やす米国株投資』など。
岡元 兵八郎のプロフィールを見る

