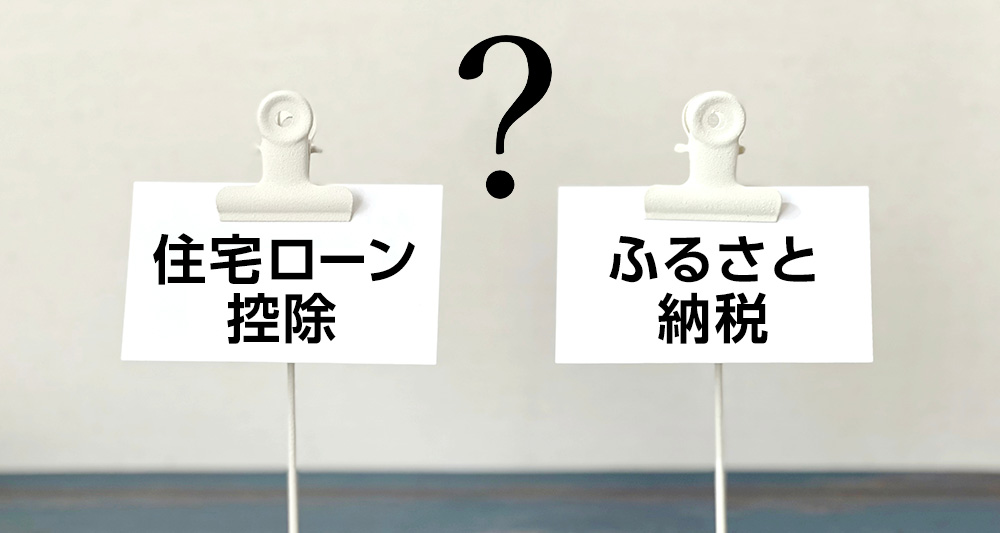【この記事を読んでわかること】
- 住宅ローン控除を利用すると最長13年にわたって所得税・住民税の税額控除が受けられる
- 住宅ローン控除の受けられる期間が終わると、所得税・住民税から控除を受けていた分の税負担が増えてしまう
- 住宅ローン控除が終わったらiDeCoの利用や繰上げ返済を検討
住宅ローンを組んで住宅を購入すると、条件に当てはまる方は住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けられ、税負担が軽くなるメリットがあります。とはいえ、住宅ローン控除はいつまでも利用できるものではありません。住宅ローン控除の期間が終わると、税負担が増えてしまいます。
今回は、住宅ローン控除が終わったらどれくらい税金が増えるのか、紹介します。
※ 定期的に税制改正が行われており、この記事では2024年11月時点の制度についてご紹介します。
住宅ローン控除の控除期間は?
住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて住宅を購入・リフォームした人が節税できる制度。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除を利用すると、所定の期間にわたって所得税や住民税を控除することができるため、税負担が軽くなります。
2022年以降の住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高の0.7%に当たる金額を最大13年にわたって所得税から控除できます。所得税から控除しきれない分は、住民税からも控除できます(ただし、住民税から控除できる金額は「前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで」となっています)。
住宅ローン控除では、購入した時期や、購入した住宅の種類、新築か中古かによって、控除が適用されるローン残高(借入限度額)や控除期間が変わります。
<住宅ローン控除の借入限度額と控除期間>
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 2023年 |
2024年 | 2025年 | |||||
| 一般の世帯 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯※1 |
||||||
| 新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,500万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
4,000万円 |
3,000万円 | |||
| その他の住宅 | 3,000万円 | 0円※2 | 0円※2 | 0円※2 | |||
| 既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
3,000万円 | 10年 | |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 |
2,000万円 |
2,000万円 | |||
この表は横にスクロールできます
※1 19歳未満の子のいる世帯または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯
※2 2023年中に建築確認を受けている場合・2024年6月30日までに建築された場合は2,000万円、控除期間10年
(株)Money&You作成
なお、2024年時点では、子育て世帯・若者夫婦世帯の新築の借入限度額が多くなっています。本稿執筆時点ではまだ確定していませんが、2025年についても同様になると見込まれています。
住宅ローン控除終了後の負担増はいくら?
たとえば、2024年に一般の世帯の人(会社員・独身)が新築の省エネ基準適合住宅に入居し、13年後の2037年まで住宅ローン残高が3,000万円以上残っていたとします。
この場合の控除額は次のようになります。
-1年間で控除できる金額:3,000万円×0.7%=21万円
-13年間で控除できる合計の上限額:21万円×13年=273万円
年収が仮に600万円(所得控除は基礎控除と社会保険料(年収の15%)のみ)の場合、税額は以下の通りです。
-所得税:約20.7万円
-住民税:約30.8万円
住宅ローン控除を利用すると、1年間で21万円分控除することができるので、所得税を20.7万円分、残りの0.3万円(21万円-20.7万円)分を住民税から減らし、
-所得税:ゼロ
-住民税:約30.5万円
にすることができます。
しかし、13年間の控除期間が終わり2038年になったら、住宅ローン控除が利用できなくなってしまうため、21万円の控除が受けられなくなり負担が増えます。
なお、13年間にわたって住宅ローン控除を満額受け続けられる人は少ないかもしれません。住宅ローン控除は「年末時点の住宅ローン残高の0.7%に当たる金額」を軽減するからです。13年のうちに住宅ローンの返済が進み、住宅ローン控除の借入限度額(今回の試算で言えば3,000万円)を下回れば、住宅ローン控除で軽減できる金額は少なくなっていきます。
住宅ローン控除が終わったらどうしたらいい?
13年(または10年)にわたる住宅ローン控除が終わると、単純に税負担が増えてしまいます。その金額は個人により異なりますが、数十万円に及ぶ場合もあります。
この税負担を減らすために検討したいのが、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の利用です。
iDeCoは、自分で拠出した掛金で運用を行い、その成果を60歳以降に受け取る制度。国民年金・厚生年金といった公的年金に上乗せする「自分年金」が作れる制度です。
iDeCoの大きなメリットの1つに「掛金が全額所得控除される」ことがあります。iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になるため、所得税・住民税を減らすことができます。
住宅ローン控除終了後にiDeCoを利用することで、税負担を減らせます。
たとえば、前述の600万円(所得控除は基礎控除と社会保険料(年収の15%)のみ)の方であれば、所得税率は10%、住民税率は所得税にかかわらず一律で10%です。
iDeCoに毎月2万円(年24万円)を積み立てたとすると、所得税が年2万4,000円、住民税が2万4,000円、合計4万8,000円も税負担を減らすことができます。
iDeCoは会社員の場合65歳になるまで掛金を出すことができるので、仮にこれを20年続けたとしたら96万円の税負担の軽減につながります。
また、住宅ローン控除が終わったからこそ、預貯金に余裕があるのであれば、住宅ローンの繰上返済を検討するのも手です。
住宅ローンの繰上返済は、毎月の返済とは別にまとまった金額(一部または全額)を予定より早く返済する方法です。繰上返済をすることで、住宅ローン残高の元金を減らすことができます。元金を減らせれば、支払う予定の利息も減らすことができるため、返済総額を減らすことができます。
繰上返済には、「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。
期間短縮型は、毎月の返済額はそのままで、返済期間を短くする方法です。たとえば、残り22年の住宅ローンを15年にする場合などが該当します。
一方の返済額軽減型は、返済期間はそのままで、毎月の返済額を軽減する方法です。たとえば、毎月9万円の支払いを8万円に軽減する場合などがあります。
総返済額を減らす効果は期間短縮型の方が大きくなります。ただ、毎月の返済額を減らして月々の家計を楽にしたいというのであれば、返済額軽減型も選択肢に入るでしょう。
ただし、繰上返済には手数料がかかる場合があります。繰上返済手数料は、お借入れの金融機関や手続き方法によって異なります。一部繰上返済の場合や、インターネットでの手続きの場合は手数料が無料になるケースもありますが、全額繰上返済や窓口での手続きの場合は数万円程度の手数料がかかることもあります。
住宅ローン控除の期間が終了したら、当然ながらその分の税負担が増えます。
軽減率は異なりますが、iDeCoを利用すれば、将来に備えながら税負担を軽くできます。また、住宅ローン控除中は見送っていた「繰上返済」を行うことも一つの手です。
※本ページは2024年11月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下の留意点を必ずご確認ください。

頼藤 太希
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
頼藤 太希のプロフィールを見る