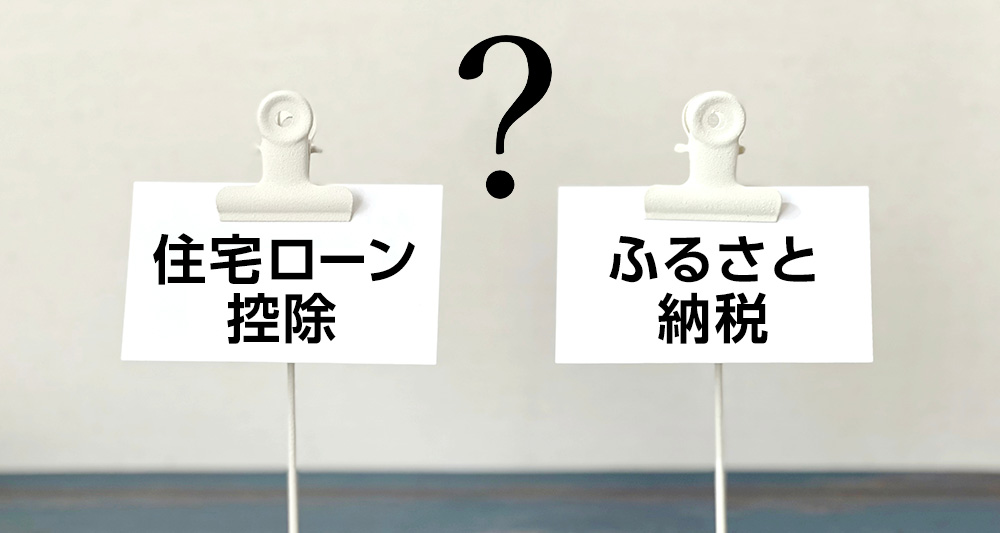【この記事を読んでわかること】
- 「パワーカップル」とは、厳密な定義や年収基準はないが、夫婦ともに年収が高い共働き夫婦のことをさす。
- 夫婦で住宅ローンを借りる方法には、ペアローン、収入合算(連帯債務)、収入合算(連帯保証)の3つがある。
- パワーカップルが住宅ローンを組む場合には、借入額が高額になりやすいので、無理のない返済を計画する。特に目先のメリットを重視しがちになるが、離婚や夫婦の一方が亡くなった場合などさまざまなリスクも考慮に入れて、ローンの借り方を考える。
近年、巷で耳にするようになった「パワーカップル」。名前だけは知っているが意味はよく知らない、という方も多いのではないでしょうか。夫婦2人の収入を合わせることで、思い描いた高額物件を手に入れられる可能性が高まるとなれば、夢もふくらみます。
今回は「パワーカップル」の定義や住宅ローンの組み方、住宅ローンを組む際に気を付けるポイントを解説していきます。
パワーカップルの住宅選び
そもそも「パワーカップル」とはどういった意味かというと、夫婦ともに年収が高い共働き夫婦のことをさします。厳密な定義があるわけではありませんが、ニッセイ基礎研究所によれば、夫婦ともに年収700万円超の夫婦としています。夫婦合わせると年収1,400万円以上の世帯ということです。一方、三菱総合研究所によれば、夫の年収600万円以上、妻の年収400万円以上の夫婦で、合わせて年収1,000万円以上としており、ともに経済的に余裕がある世帯をさします。
世帯の構成は、夫婦だけでバリバリ仕事をこなしているイメージが強いのですが、ニッセイ基礎研究所によれば、夫婦と子の世帯が60%、夫婦のみの世帯が35%という内訳になっています。子どもがいるとなると忙しくなるため、仕事と家庭の両立のために時短食材や時短家電、家事代行サービスなどを利用して時間の確保をしている世帯も多くなっています。
収入と住宅ローンの関係でいうと、一般的には年収の5倍から7倍の借入額が基準だといわれています。しかしながら、都心では投資マネーの流入などで新築マンション価格が上昇しているため、年収の7倍から10倍の価格になることもあります。不動産経済研究所の調べでは、2024年8月の首都圏新築マンションの平均価格は9,532万円です。東京都23区内では、平均1億3,948万円とさらに高額です。
たとえば、世帯収入を1,000万円とするパワーカップルの場合には、借入額の基準を5倍から7倍だとすると、5,000万円~7,000万円の借入が可能になります。国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によれば、住宅購入資金のうち借入額の平均は以下のようになっています(注文住宅では全国での調査、その他の住宅は三大都市圏での調査)。
いずれの住宅取得の場合にも3割から4割程度の自己資金を用意して購入しています。
| 土地を購入した注文住宅新築 | 4,126万円 |
| 分譲戸建住宅 | 2,985万円 |
| 分譲集合住宅 | 2,437万円 |
| 中古戸建住宅 | 1,573万円 |
| 中古集合住宅 | 1,456万円 |
- 出典:「令和5年度住宅市場動向調査報告書」国土交通省
パワーカップルなら高額物件に手が届きやすく、住宅購入の選択肢が広がりますが、夫婦双方が現在の収入を維持できるとは限りませんし、固定資産税や修繕積立金など住宅取得によってかかる費用も増えます。
教育費や老後資金など、住宅以外のお金も必要です。
将来の不確実性に柔軟に対応するには、借入額は世帯年収の5倍以内が目安になります。
住宅ローンの借入可能額の算出方法は年収ベースで金融機関が貸してくれる金額ではなく、家計に応じて無理なく返済できる金額から求める方法もあります。たとえば、手取りから住宅ローンに回せる毎月の返済額が15万円だとすると、金利が1%の場合には30年返済で4,663万円、35年返済で5,313万円の借入が目安になります。マンションでは、管理費・修繕積立金、駐車場代がかかるため、これらの支出を差引いて返済額を考えます。ただし、金利を高く見積もると借入可能額は当然少なくなります。
パワーカップルなら、1人で借りるより夫婦で借りるほうが借入額を増やすことができ、理想の住宅を購入しやすくなるでしょう。
夫婦2人で住宅ローンを組む方法には、主に「ペアローン」と収入合算して借りる方法で「連帯債務」と「連帯保証」の3つがあります。それでは内容を見ていきましょう。
ペアローン・収入合算どっちを選ぶ?
ペアローンは、一つの物件に対し、夫婦それぞれが住宅ローンを契約するものです。
2人がそれぞれローンの債務者となって返済し、お互いが相手の連帯保証人になります。ペアローンは別々の契約なので、借入額や金利のタイプ、期間などの契約条件を個別に設定することができます。所有権は共有名義になり、持分は資金の負担の割合と同じにするのが基本です。住宅ローン控除も2人分利用が可能です。
夫婦の収入を合算して1本のローンとして借りる方法のうち、連帯債務は夫婦の片方が債務者、もう片方が連帯債務者になり、2人とも同等の返済義務を負います。夫も妻も債務者となるため、所有権は共有名義になり、住宅ローン控除はそれぞれが利用できます。
連帯保証は、夫婦の片方が債務者、もう片方は連帯保証人になり、連帯保証人は債務者の返済ができないときに返済義務が生じます。住宅ローン控除は債務者のみが利用でき、所有権は連帯保証人が頭金を出した場合を除き、債務者の名義になります。
<夫婦で住宅ローンを組む方法>
| ペアローン | 収入合算 | ||
|---|---|---|---|
| 連帯債務 | 連帯保証 | ||
| 借り方 | 夫婦が1本ずつローン契約 | 片方が主債務者、もう片方が連帯債務者 |
片方が債務者、もう片方が連帯保証人 |
| 返済義務 |
互いに相手の連帯保証人 | 2人とも返済義務あり | 債務者が返済できないときに連帯保証人に返済義務 |
| 住宅ローン控除 | 2人とも対象 | 債務者が対象 | |
| 事務手数料 | 2人分 | 1人分 | |
| 所有権 | 共有名義 | 債務者名義 | |
| 団信への加入 | それぞれ加入 | 主債務者が原則加入 | 債務者が加入 連帯保証人は加入できない |
筆者作成
ペアローンのメリットとデメリット
ペアローンのメリットの1つは、単独ローンにくらべると借入額が増やせることです。2人の収入全額を合算できるため、より多く借りることができます。2本のローン契約であるため、夫婦2人とも住宅ローン控除の対象になります。
デメリットは、ローンを2つ組むことになるので、事務手数料や団体信用生命保険(団信)の保険料などの諸費用が2つかかることです。ペアローンでは、団体信用生命保険(団信)にも夫婦各自で加入することになります。もしも夫に万が一のことがあった場合には夫の住宅ローンは完済されますし、妻の場合には妻のローンが免除されます。ただし、もう一方のローンは残ります。
収入合算のメリットとデメリット
収入合算のメリットは、ペアローンと同じように2人の収入を合算して借りることができることです。ただし、金融機関には連帯保証の場合、連帯保証人の収入を全額合算しないところもあります。1本のローンのため、事務手数料は1人分で済みます。
デメリットとしては、連帯保証の場合には、住宅ローン控除が債務者のみの利用になることです。通常住宅ローンを借りるときには、団体信用生命保険(団信)に加入のが原則です。返済中に債務者が亡くなった場合は住宅ローンはゼロになりますが、連帯債務者や連帯保証人が亡くなった場合はローンが残ります。連帯債務では、債務者だけでなく連帯債務者が亡くなってもローンが完済される「連生団信」を扱う金融機関もあります。
パワーカップルの住宅ローンで気を付けるべきポイントは?
夫婦ともに高収入になると、住宅ローンが高額になりがちです。子どもがいれば、育児休業や時短勤務などで減収になることも計算に入れて、無理なく返済に対応できるようにしておきましょう。もしも減収などで返済に行き詰れば、自分のローンを返済しながら相手の返済責任も負うことになります。収入が高いから大丈夫と思わず、無理のない返済計画にしておくことが大切です。
また、住宅ローンの金利が上昇傾向で、将来いくらまで上がるのか不安に感じている方も多いでしょう。ペアローンを組む場合には、片方を固定金利で借入期間を長期で設定し、もう片方を変動金利で借入期間を短くするなど、完済時の年齢や返済期間などを調整することで、家計運営がしやすくなります。
住宅ローン返済中の夫婦の片方が亡くなった場合の備えについても考えておきましょう。共働き世帯の場合、夫婦いずれかの収入がなくなると、ローン以外の出費をすべて1人で賄うことになります。ペアローンのうち1本がなくなっても安心とはいえません。また、連帯債務で契約し夫婦連生団信でローンが完済されたときに、所得税がかかることがあります。夫婦連生団信とは、万一夫婦のどちらかが亡くなった場合などに残された方の分もローンが完済される仕組みです。返済を免除された方の分については、一時所得とみなされる場合があります。連生団信を契約している場合には、貯蓄や生命保険でその他の資金を準備するなど、万が一のことも検討しておくと安心です。
ペアローンや連帯債務では、所有権にも注意が必要です。共有名義にすることが一般的ですが、負担と所有権登記の持分の割合が違うと、夫婦間で贈与があったとみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。
さらに、夫婦で住宅ローンを借りる際の最大リスクは離婚といわれています。離婚をしても契約関係は変わらず、自宅の所有権やローンの返済をどうするかで協議が難航しやすいからです。夫婦が仲良く働いて住宅ローンを返済していくのが、夫婦で住宅ローンを借りる前提なのです。
メリットばかりではなくリスクにも目を向ける
パワーカップルの住宅ローンの借入れは、借入額が膨らんで将来の返済が厳しくなる恐れがあります。「購入できるか」より「返済できるか」を重視しましょう。
単独ローン以上に計画性をもって入念な検証が必要になります。夫婦で住宅ローンを組むことは、条件のいい高額物件も購入対象になる一方で、収入減になれば家計が不安定になりやすい落とし穴もあります。借入額が大きいだけに、返済中の夫婦のうちの一方が死亡したときの備えなど単独ローンにないリスクも抱えています。
借入額が増やせることや住宅ローン控除が利用できるメリットだけにとらわれることなく、さまざまなリスクにも目を向けてローンの借り方を考えましょう。
- 本ページは2024年12月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
オススメ

池田 幸代
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
池田 幸代のプロフィールを見る