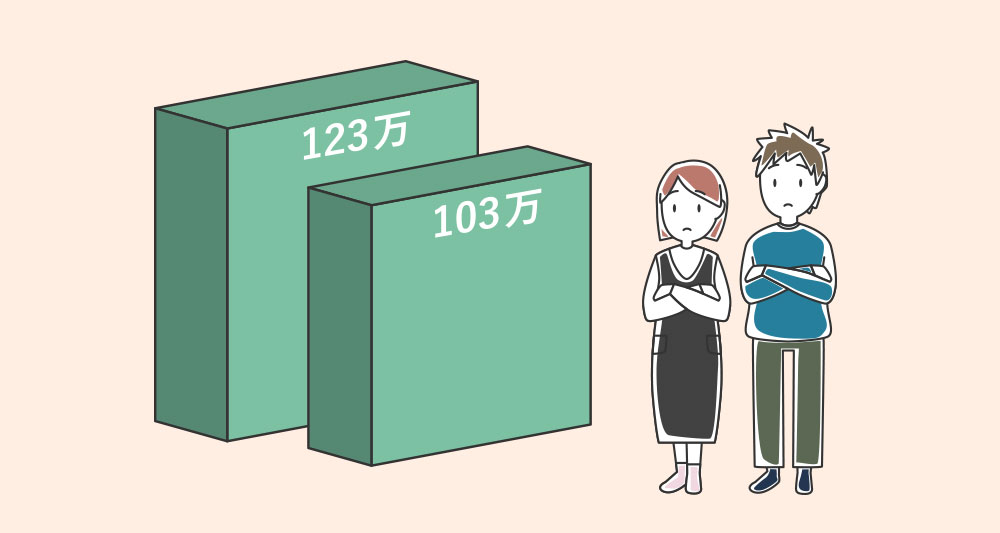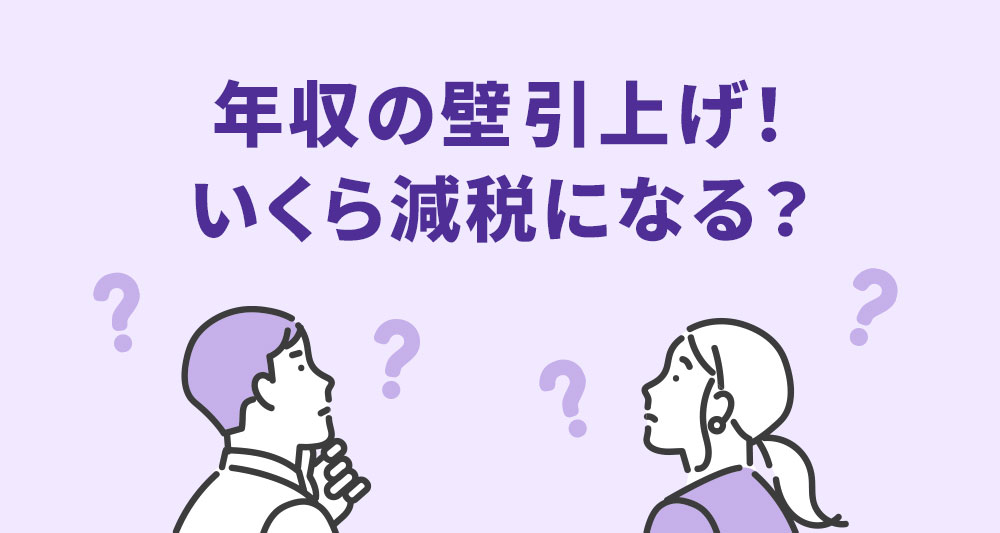


ざっくり言うと…
- ドラッグストアで買う市販薬が年間12,000円を超える場合、税金の控除が受けられる場合がある
- 対象市販薬にはパッケージにロゴマークがついている
- 所得400万の方が対象市販薬を年間50,000円購入したら、11,400円の減税効果
- 申請するためには、購入した領収書やレシートが必要
ドラッグストアで胃腸薬、鎮痛剤、抗アレルギー薬、花粉治療薬などの市販薬を買った時にもらえる領収書やレシートを「必要ないから」と捨ててしまっている方も少なくないのではないでしょうか。
実は2017年1月からスタートした「セルフメディケーション税制」で、税金の控除を受けられるようになったのです。
1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用される「医療費控除」は比較的よく知られている制度ですが、セルフメディケーション税制は知っている方はまだまだ少ないのではないでしょうか。ですが、市販薬の購入金額が年間12,000円を超える部分の金額が、税金の控除となり、適用される方は少なくないはずです。
セルフメディケーション税制とは?
具体的には、予防接種や定期健康診断など「日ごろより健康増進や病気予防のために一定の取り組み※を行っている人」が、2017年1月1日以降(2021年12月31日まで)に、自分または生計を一にする家族のために対象医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した際に、1万2,000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8,000円)について所得控除を受けることができます。
簡単にいうと、「日ごろから健康増進・病気予防に努めている人が対象の市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合には、税金面で優遇しますよ」、という制度です。
- 「一定の取り組み」について厚生労働省のホームページでは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診が挙げられています。
どれくらい税金が安くなるの?
では、実際にこの制度を活用すると、どのくらいおトクになるのでしょうか?
ここでは、課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間5万円購入した場合を考えてみます。なお、この購入金額には「生計を一にする家族の分」も含まれます。
控除額
50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
減税額※
所得税:38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円
個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円
所得税・住民税合計で11,400円の減税効果!
「税金の控除(こうじょ)ってなに?」という方は、以下の関連コラムを参考にしてください。
対象となる市販薬は?
まず、制度の対象となる市販薬は、薬局やドラッグストアで購入できる医療用成分が配合された市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているものになります。
スイッチOTCとは、従来は医師の処方箋が必要だった医療用医薬品の中から、薬局で購入できるよう、一般用医薬品に転用されたものです。
テレビコマーシャルでおなじみの胃腸薬、鎮痛剤、抗アレルギー薬、花粉治療薬などの中にもこれに該当する医薬品があります。


基本的に対象商品のパッケージには、セルフメディケーション税制が適用になる商品だとわかる「ロゴマーク」がつきますが、生産の都合などの理由により、このロゴマークが表示されていない対象商品もあります。
たくさん売れている商品は対象市販薬であることがわかるようにお店で掲示されている場合もありますが、ロゴマークが表示されていない商品が対象市販薬かどうか不明な場合には、店員さんに確認するか、以下の厚生労働省のウェブサイトでの確認が必要になります。
どうやって申請すればよいの?
セルフメディケーション税制を利用して税金の控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告は、年間(1月~12月まで)の関連書類をまとめて翌年の2月16日から3月15日までに手続きを行うことになりますが(*1)、セルフメディケーション税制を利用する場合には購入した対象医薬品の領収書やレシートを5年間保管しておく必要がありますので、間違って捨てたり無くしたりしないように注意しましょう。
お店ごとに異なりますが、領収書やレシートに該当商品を購入したことを示す記載があります。
さらに、セルフメディケーション税制を受けるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など、日ごろより健康増進や病気予防に取り組んでいることが条件になります。
ですから、これらの検診を受けた時の領収書や結果表も必要になります。こちらもあわせて保管しておきましょう。
みなさんの中には、「確定申告」という言葉を聞くだけで、「難しそう」「自分にはムリ」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえば国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」なら初心者でも比較的カンタンに確定申告書等を作成することができると思います。ぜひチャレンジしてみてください。
- 確定申告の手続きや期限などについて、詳細は国税庁のホームページまたはお近くの税務署でご確認ください。また、「還付申告」(納めすぎた税金を返してもらう手続き)の場合は翌年1月から5年間申告することができます。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
注意点として、1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用される「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」どちらも利用できるのかというと、併用はできません。
従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。
例えば、年間で11万円医療費を使った場合で見てみましょう。
パターン1
11万円の内訳が「ドラッグストアで購入した対象医薬品20,000円」「病院代90,000円」このような場合
医療費控除…110,000円-100,000円(下限額)=10,000円(控除額)
セルフメディケーション税制20,000円-12,000円(下限額)=8,000円(控除額)
パターン2
11万円の内訳が「ドラッグストアで購入した対象医薬品50,000円」「病院代60,000円」このような場合
医療費控除…110,000円-100,000円(下限額)=10,000円(控除額)
セルフメディケーション税制50,000円-12,000円(下限額)=38,000円(控除額)
パターン1の場合は従来の医療費控除を利用した方がおトクになり、パターン2の場合はセルフメディケーション税制を利用した方がおトクになります。
以上、セルフメディケーション税制について説明してきましたが、このようにちょっと気をつけたり、手間をかけたりするだけで、お金の節約ができる制度がいろいろ作られています。 家計の節約のために、ぜひ関心を持って情報収集してくださいね。
今回のまとめ
- 年間12,000円以上市販薬を購入していれば、セルフメディケーション税制が利用できる場合がある。
- 対象市販薬の合計金額は、生計を一にしている家族の分も合算できる。
- この制度を利用するためには確定申告が必要。領収書やレシートなどを捨てないように注意する。
- 医療費控除との併用はできないので、どちらで申告した方が節税になるかを確認する。
- 本ページは2018年1月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。

高山 一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)
(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue
高山 一恵のプロフィールを見る