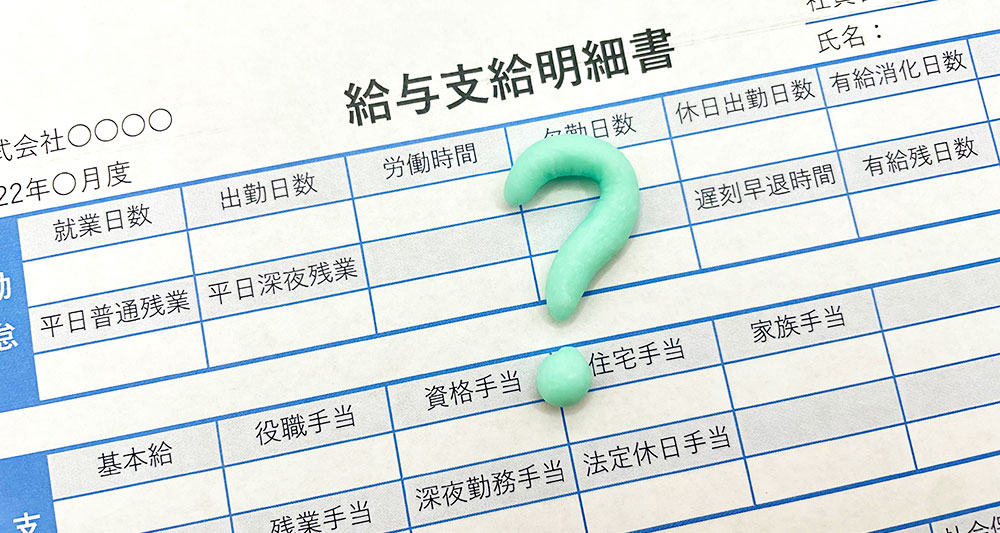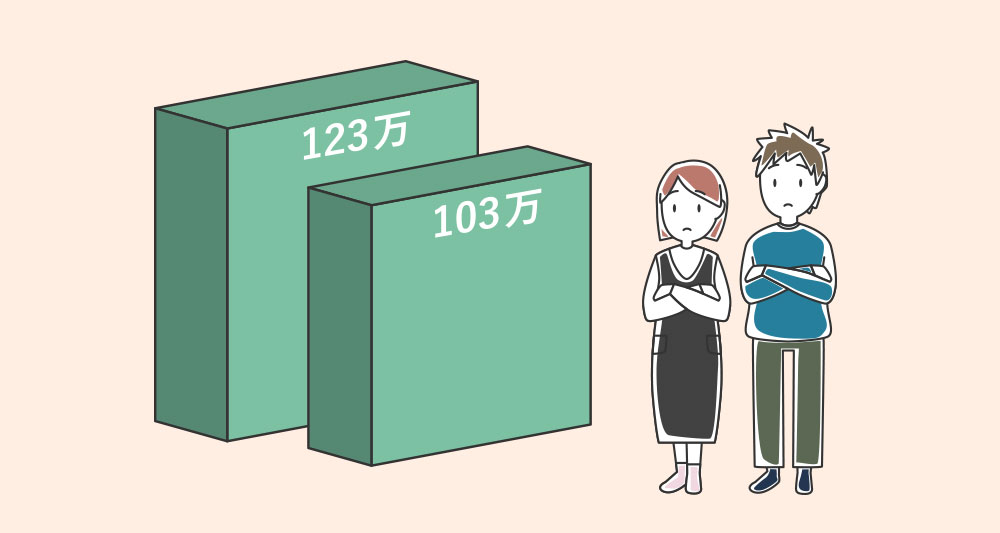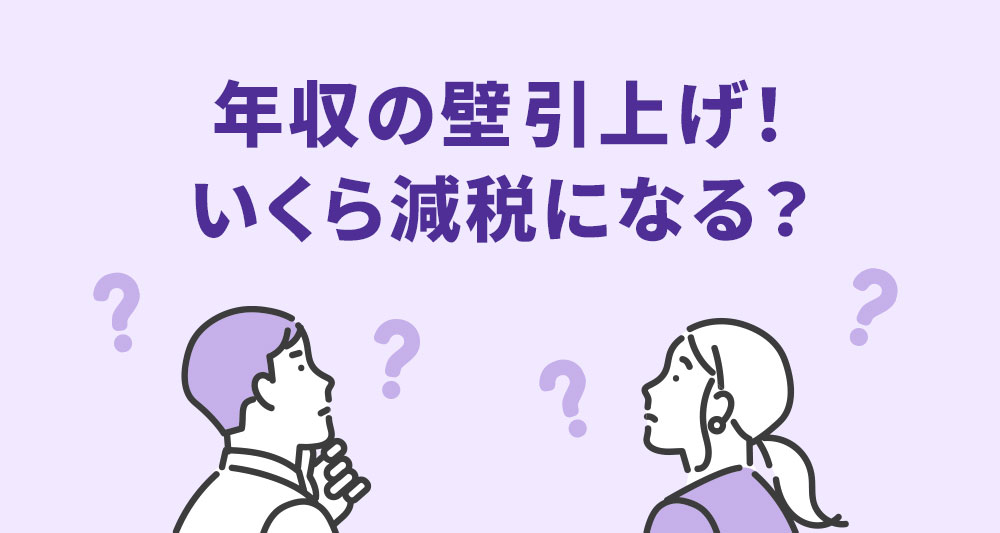
給与明細の「控除」減らせるもの・減らせないものは?
毎月の給与明細は、会社によって書式は異なるものの、おおよそ次のようなものです。
<給与明細のイメージ(40歳未満の例)>


(株)Money&You作成
控除欄には、給与から天引きされる社会保険料と税金の金額が記載されています。総支給額から総控除額を引いた差引支給額が手取りの給与です。手取りを増やすには給与からの控除額を減らせればよいというわけです。
しかし、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険といった社会保険料を減らす手立てはありません。社会保険料は給与をもとに計算されるので、あえて言えば、給与を減らせば減りますが、それでは本末転倒ですよね。
一方、所得税・住民税はさまざまな制度を利用することで減らせる可能性があります。税金も社会保険料と同様、給与をもとに計算されるのですが、その計算の過程で出てくる所得控除・税額控除といった仕組みを活用することで、税金が減らせます。
では、所得控除や税額控除が利用できる仕組みにはどんなものがあるか、確認してみましょう。
所得控除は、所得税額を計算するときに、本人や家族の状況、災害や病気といった個別の事情を税額に反映させるための制度です。全部で15種類あります。
関連記事
医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除は、1年間に負担した医療費が多くなったときに、確定申告することで節税できる制度です。所得額200万円以上の場合、年間の医療費が10万円を超えた場合に利用できます。所得額が200万円未満の場合は、年間の医療費が所得額の5%を超えた場合に利用可能です。
医療費控除の対象になる医療費は、確定申告をする本人が支払った医療費だけでなく、生計を一にする(生活費を共有している)家族の分も合算できます。
なお、医療費控除が適用できるほど医療費を支払っていない場合は、セルフメディケーション税制が利用できるかもチェックしましょう。
セルフメディケーション税制は、所定の健康診断を受けている人が特定の市販薬を購入し、年間費用が1万2,000円を超えた場合、その超過分(最大8万8,000円)が控除対象になる医療費控除の特例制度です。
医療費控除・セルフメディケーション税制の手続きには確定申告が必要です。医療費を支払ったことがわかる領収書などを確認して手続きしましょう。なお、領収書や健康診断の証明書は提出不要ですが、自宅で5年間保存する必要があるので、捨てずに取っておきましょう。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、有利な方を選んで申請しましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附をすることで、2,000円を超える金額を所得税や住民税から控除できる寄附金控除制度のひとつです。多くの場合、自治体からは返礼品と呼ばれるお礼の品がもらえます。つまり、実質2,000円で返礼品が手に入るというわけです。返礼品は各地の食料品や雑貨、日用品などさまざまで、ネットショッピングのような感覚で選ぶことができるので人気が高まっています。
正確には「節税」ではないのですが、返礼品がもらえる分、利用した方が確実におトクです。
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をする方法とワンストップ特例を利用する方法の2種類があります。このうち、確定申告の必要のない会社員や公務員ならばワンストップ特例が便利です。
ワンストップ特例は次の手続きをするだけで翌年の住民税を安くできます。
①自治体を選び、寄附をする
②自治体からお礼の品と「ワンストップ特例申請書」が届く
③ワンストップ特例申請書に必要事項を記載して、返送する
ワンストップ特例を利用するには、次の条件を満たさなければなりません。
- 年収2,000万円を超える給与所得者ではない
- 給与を複数から得ていない
- 医療費控除などの確定申告が必要ない方
- 1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以内
これらを1つでも満たさない場合は、ふるさと納税の確定申告が必要です。ワンストップ特例を申し込んだあとで、「そういえば、医療費控除もしなければならなかった」という場合には、ワンストップ特例がなかったものと見なされ、ふるさと納税の分も確定申告をしないと税金が安くなりませんので注意しましょう。
ふるさと納税で自己負担額が2,000円になる金額には上限額があり、年収や家族構成により異なります。上限額を超えても寄附はできますが、その分は自己負担になってしまいます。ですから、ですから、事前に自分がいくらまで寄附できるのかを確認した上で取り組みましょう。
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で毎月積み立てた掛金を運用し、その成果を原則60歳以降に一時金または年金の形で受け取る制度です。公的年金の上乗せとなる「じぶん年金」を作れる制度として注目されています。
iDeCoでは、掛金の「拠出時」「運用時」「給付時」の3つのタイミングで税制優遇が受けられます。
- 拠出時:毎月の掛金が全額所得控除できるため、所得税や住民税を減らせる
- 運用時:積立期間中に運用で得られた利益に税金(20.315%)がかからない
- 給付時:「退職所得控除」「公的年金等控除」の対象となり税負担を減らせる
大きいのは拠出時の税制優遇です。自分のためにお金を貯めるのに所得税や住民税まで安くできるのですから、おトクですね。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になります。10月ごろ郵送で届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管しておき、会社の年末調整の書類に必要事項を記載して一緒に提出します。
住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除は、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度です。正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。また、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅ローン控除は「税額控除」の制度です。住宅ローン控除を利用すると、新築住宅の場合13年間、中古住宅の場合10年間にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から直接差し引くことができます。また、所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます(前年度課税所得×5%、最高9万7,500円まで)。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
住宅ローン控除の適用を受けるには、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は、勤め先での年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。年末調整の時期に、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を勤務先に提出しましょう。
給与明細の控除欄にある金額のうち、社会保険料を減らすことはできないのですが、税金は各種制度を利用することで減らすことができます。自分が利用できそうな制度を確認し、もし利用できるならば積極的に利用しましょう。そして手取りの給与を増やしていきましょう。
- 本ページは2024年2月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下の留意点を必ずご確認ください。

頼藤 太希
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
頼藤 太希のプロフィールを見る