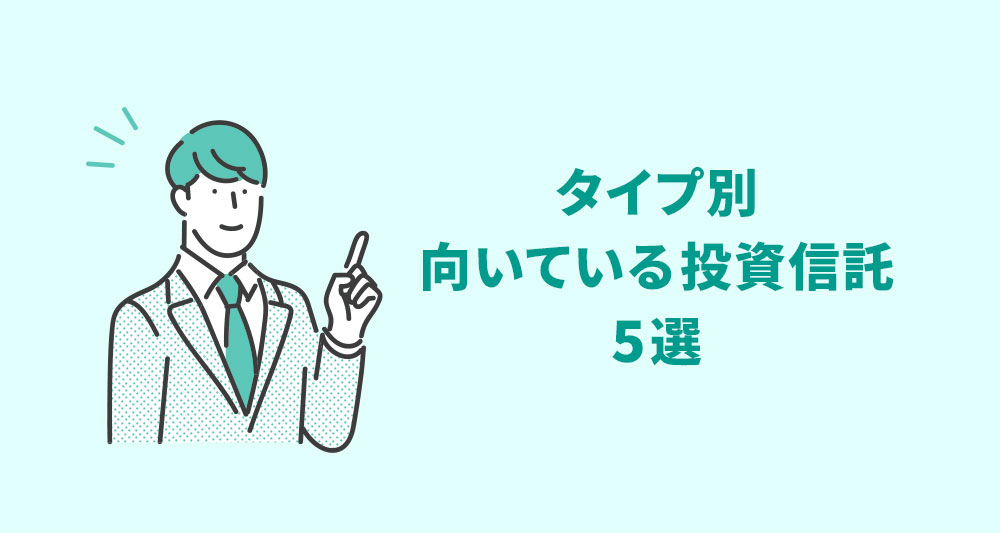
【2025年最新版】お金のプロが選ぶ、タイプ別向いている投資信託5選
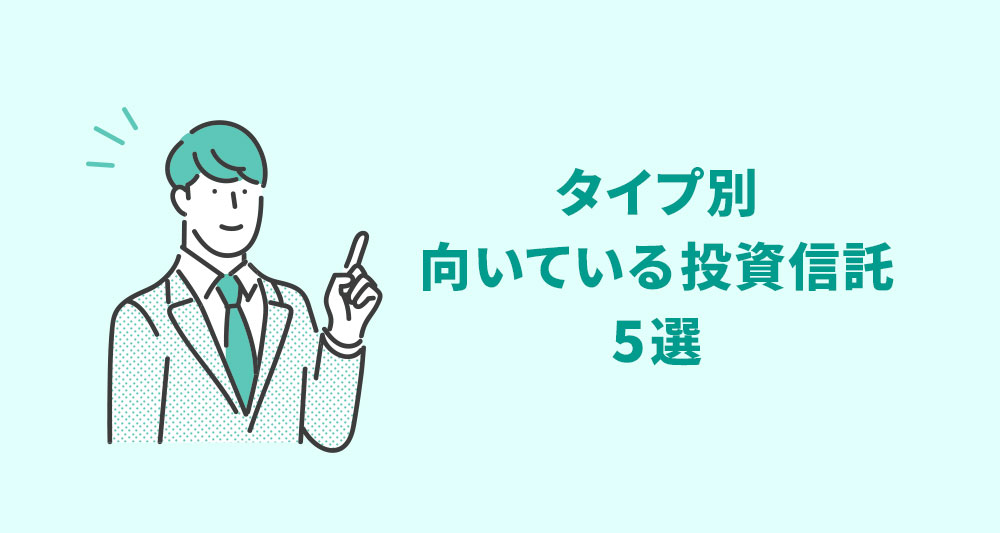
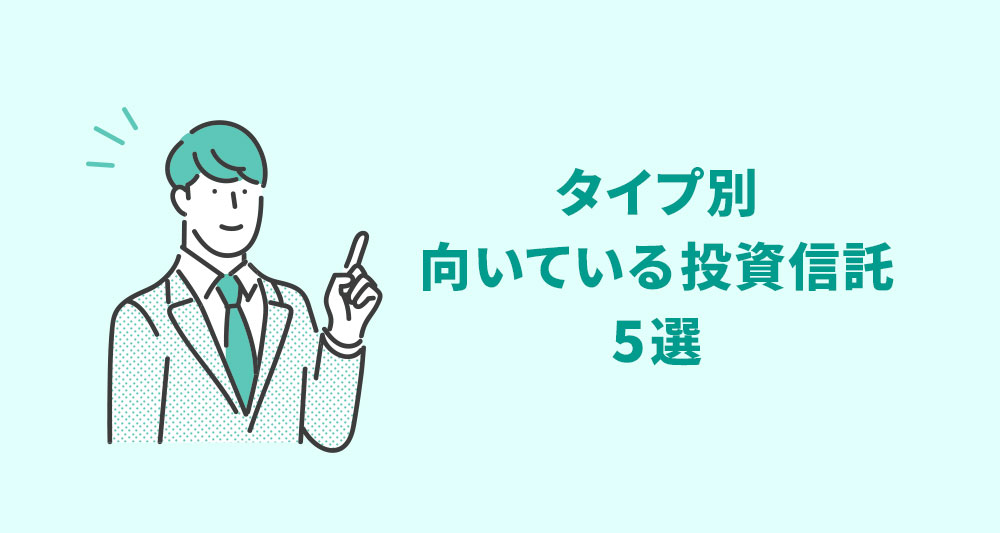
気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
【この記事を読んでわかること】
- 投資信託を選ぶ5つの基準は「アクティブ型よりもインデックス型がベター」「信託報酬・実質コストともに低いファンド」「月次資金流入が堅調で、純資産総額と基準価額は右肩上がりのファンド」「業績が安定している『運用会社』のファンド」「分散投資を意識するなら、市場カバー率は80%以上がベター」。
- お金のプロが選ぶ、タイプ別向いている投資信託を紹介。「リスクを抑えながら増やしたい方向け」1本、「積極的に増やしたい方向け」2本、「増やしつつ定期的に分配金をもらいたい方向け」2本。
2024年開始の「新NISA」は一大投資ブームを引起こしました。
NISAは、投資で得られた利益(売却益・配当金・分配金)に対する20.315%の税金がかからない制度です。なお、新NISAでは毎月分配型など一部のファンドは投資対象外となっています。分配金があるファンドであっても、新NISAの対象となるものと対象外のものがある点にご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
投資とは、値動きのある資産にお金を投ずることです。増えもするし、減りもします。2024年は概ね株式市場が好調でしたが、一方で8月には大暴落がありました。この暴落では多くの人が資産を大きく減らすことになりました。中には精神的に疲弊してしまった方もいたかもしれません。
まだ投資をはじめていない方にとっては、暴落は未知の領域かもしれませんが、投資とはそういった負の感情とも上手く付き合いながら続けていくものです。
≫関連コラム
株価大暴落時に慌てて売却はNG?投資初心者が知っておくべき対策
さて、2025年は新NISA2年目です。読者の中には、これからはじめたいという方や、改めて投資先を見直したいという方もいることでしょう。
今回は、投資信託を選ぶ5つの基準を紹介し、タイプ別おすすめ投資信託をご紹介します。
よい投資信託を選ぶ5つの基準
基準1:アクティブ型よりもインデックス型がベター
投資信託は、運用方法の違いによって「インデックス型」と「アクティブ型」にわけることができます。日本株価指数「TOPIX」、米国株価指数「S&P500」、全世界株価指数「MSCI ACWI」といった特定の指数をベンチマークにして連動を目指すのがインデックス型です。ベンチマークである指数よりも高い運用成果や、特定のベンチマークを設けず「年10%」などと絶対収益を掲げて運用するのがアクティブ型です。
どちらを選んだ方がよいか、筆者の結論は「インデックス型」です。
理由の1つはインデックス(指数)に勝てないアクティブ型がほとんどであることです。もう1つは、保有中のコストがアクティブ型と比べてインデックス型は圧倒的に低いことです。
まず過去の運用成績では、長期の運用になればなるほど、アクティブ型はインデックス型(指数)をほとんど上回っていません。「SPIVA日本スコアカード(2024年上半期版)」によると、アクティブ型の投資信託を10年・15年運用した時点で、インデックス型を上回っていないファンドが約85~100%であることがわかります。
<インデックス型を上回らなかったアクティブ型の割合>
- この表は横にスクロールできます
| ファンド・カテゴリー | 比較指数 | 年初来 (%) |
1年 (%) |
3年 (%) |
5年 (%) |
10年 (%) |
15年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大型株ファンド | S&P/TOPIX 150 指数 | 69.77 | 70.23 | 80.67 | 88.63 | 87.30 | 84.91 |
| グローバル株式ファンド | S&P ワールド指数 | 80.98 | 75.00 | 95.53 | 95.33 | 99.16 | 100.00 |
| 米国株式ファンド | S&P 500 | 77.68 | 74.53 | 94.59 | 90.43 | 91.55 | 91.30 |
| 新興国株式ファンド | S&P 新興国総合指数(BMI) | 86.15 | 95.00 | 88.41 | 91.25 | 100.00 | 100.00 |
S&Pダウジョーンズ社「SPIVA日本スコアカード(2024年上半期版)」より
日本の大型株ファンドは善戦してはいますが、将来も上回り続ける保障はありません。将来も上回り続けるアクティブ型を選ぶにはそれなりの選択眼を養う必要があります。
加えて、アクティブ型の信託報酬(投資信託保有中のコスト)は年およそ1〜2%(この範囲に収まらないファンドも存在いたします)と高く、信託報酬を踏まえて、インデックスのパフォーマンスを超えているファンドはもっと少なくなります。信託報酬は、運用成績が悪くても毎日支払う必要がある手数料です。
基準2:信託報酬・実質コストともに低いファンド
「インデックス型だから、コスト面で安心」とはならないのが難点です。
というのもインデックス型の中でも信託報酬に差があるからです。年0.1%を下回るファンドもあれば、年0.6%程度のファンドも存在します。しかも、そうしたややコストが高めのインデックス型が新NISAのつみたて投資枠やiDeCo(イデコ)の商品に含まれているケースもあるため、注意が必要です。
信託報酬は保有している間にかかるものですから、投資家目線に立てば当然低い方がよいです。投資期間が長くなればなるほど、少しの差でもやがて大きな差になります。
投資家に人気のある商品に「オルカン」があります。オルカンは、三菱UFJアセットマネジメントが運用する投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の略称です。人気の理由は、信託報酬が年0.05775%と超低コストファンドだからです。
インデックス型の中で、同じ指数に連動する商品なら運用成績に差はほぼなくなります。ということは、理論上は信託報酬の差が資産額に影響してくるだろうと考えられます。
なお、信託報酬だけ見ていればOKということでもありません。実際に投資家が負担した手数料は「実質コスト」です。実質コストの確認は必ずしましょう。
信託報酬自体が安く抑えられていても、その他の手数料がかかり、想定以上の負担をしている場合が結構あります。低い信託報酬だけ見て購入していたら、実際には年1%を超える手数料を負担していたということもあります。
投資信託の実質コストは、運用開始から1年経過後に出される運用報告書でわかります。したがって、本当にコストの安い投資信託を選ぶには下記の流れで探すとよいでしょう。
①運用から1年以上経過しているファンドの中から
②信託報酬で手数料の安い商品を選び
③運用報告書に記載の実質コストが安いものを選ぶ
基準3:月次資金流入が堅調で、純資産総額と基準価額は右肩上がりのファンド
純資産総額は投資信託が組入れている株式や債券などの資産の時価総額です。基準価額は純資産総額を投資信託の総口数で割って算出した投資信託の値段を表します。
この純資産総額と基準価額は右肩上がりのファンドを選ぶのが大切です。
純資産総額と基準価額が右肩上がりになるためには、下記のポイントを意識しましょう。
①投資家からのお金が断続的に流入すること(月次資金流入が堅調であること)
②安定的に運用パフォーマンスを出すこと
②の方が重要に感じてしまうかもしれませんが、①の方が影響は大きいです。
月次資金が流出するということは、投資信託の中で保有している株式や債券などの資産を売却して、投資家へ解約金として渡しているということです。
投資信託の運用方針に沿った運用を行うためには、相応のお金が必要です。お金が集まらず資金流出が続けば、商品性を維持できなくなったり、効率的な運用ができなくなったりします。
月次資金の流出が続き、純資産総額が減少していくと、最終的に「繰上償還」になる可能性があります。繰上償還とは、運用会社が運用を終了し、その時点での資産額で資金が返還されることです。
もしも繰上償還が行われる時点で運用損を抱えていたら、その損が強制的に「実現損」になります。その後の回復や値上がりを待つことができなくなるのですから、これはマイナスです。投資方針に沿った運用を実現するには、純資産総額はある程度大きくなければならないといわれています。
基準4:業績が安定している「運用会社」のファンド
低コストファンドが増えている昨今、運用会社の業績が重要になってきました。
新NISA対象ファンドを提供していた「PayPayアセットマネジメント」は、2024年10月11日、2025年9月末をめどに事業を終了することを発表しました。理由は、5期連続の赤字を計上していたためです。
これにより、運用商品12本のうち、4本は繰上償還、8本はアセットマネジメントOne株式会社に変更され、引続き運用が行われることとなりました。上述した繰上償還は、このように運用会社の業績でも起こるのです。
インデックス型は信託報酬が安いうえに、引下げ合戦が行われています。そんななか、お金の集まらないファンドを運用しつづけても運用会社は赤字が続くだけなので、運用を途中で打ち切る(=繰上償還)というわけです。運用会社の業績は、財務情報(決算公告)で確認できます。事業継続に懸念がないか、各運用会社のウェブサイトで調べてみるのもよいかもしれません。
実際、投資信託は人気のある商品とそうでない商品に二極化しています。
新NISAやiDeCoの対象商品であっても、繰上償還される投資信託は今後たくさんあるでしょう。新NISA「つみたて投資枠」の対象商品は現状約300本あります。この中から50本、100本などと繰上償還になる商品が出てきてもおかしくありません。
基準5:分散投資を意識するなら、市場カバー率は80%以上がベター
リスクを抑えながらリターンを高めたい場合には、市場全体をカバーする商品を選んだ方がベターです。多くの銘柄に投資をしている方が分散投資効果は高くなっていきます。ただし、市場カバー率(株式市場の時価総額に占める割合)の目安は「80%」です。
市場カバー率は80%を超えてくると、分散投資効果は高まりづらくなります。つまり、カバー率80%と100%で比べてみると、リスクやリターンはほぼ変わらないという状況になります。
例えば、米国株価指数には「CRSP US Total Market Index」と「S&P500」があります。CRSP US Total Market Indexは大中小型株約3600銘柄で構成されていて、米国株式市場カバー率はほぼ100%です。S&P500は大型株500銘柄で構成され、米国株式市場カバー率は80%です。カバー率は20%の差がありますが、両者のリスク・リターンは似たような水準となっています(観測時期や計測期間によってどちらが「高い」「低い」はあります)。
お金のプロが選ぶ、タイプ別向いている投資信託
上記の基準を踏まえて、タイプ別向いている投資信託を選びました。以下、断りがなければ2025年3月6日時点の数字です。
【リスクを抑えながら増やしたい方向け】
- 投資信託(1):ニッセイ・インデックス・バランスファンド(4資産均等型)
設定日:2015年8月27日
純資産総額:735 億円
基準価額:18,266 円
信託報酬(税込):年0.154%
実質コスト:0.168%(2023年11月21日~2024年11月20日)
トータルリターン(5年):年9.50% ※2025年2月28日時点
シャープレシオ*(5年):1.18 ※2025年2月28日時点
*リスクに見合った収益を測る指標。数字が大きいほどよい
日本と先進国の株式と債券に25%ずつ投資する「4資産均等型」と呼ばれるバランス型の投資信託です。株式と債券の比率が50%、国内と海外の比率も50%となるため、今回紹介する投資信託の中では、よりリスクを抑えながら堅実に増やす期待ができる資産配分です。
【積極的に増やしたい方向け】
- 投資信託(2):eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
設定日:2018年10月31日
純資産総額:5兆4,816億円
基準価額:26,442円
信託報酬(税込):年0.05775%
実質コスト::年0.194%(2023年4月26日~2024年4月25日)
トータルリターン(5年):年19.58% ※2025年2月28日時点
シャープレシオ(5年):1.24 ※2025年2月28日時点
MSCI ACWIとの連動を目指す投資信託です。世界株式市場カバー率は85%です。超低コストで、世界中の株式に分散投資が可能となっています。「eMAXIS Slim」シリーズには純資産総額が増えるごとに実質的な信託報酬率が下がる「受益者還元型信託報酬」という仕組みがあります。
- 投資信託(3):eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
設定日:2018年7月3日
純資産総額:6兆6,471億円
基準価額:31,617円
信託報酬(税込):年0.09372%
実質コスト::年0.104%(2023年4月26日~2024年4月25日)
トータルリターン(5年):年23.46% ※2025年2月28日時点
シャープレシオ(5年):1.38 ※2025年2月28日時点
S&P500との連動を目指す投資信託です。米国株式市場カバー率は80%です。超低コストで、米国株式市場全体に分散投資が可能となっています。「eMAXIS Slim」シリーズには純資産総額が増えるごとに実質的な信託報酬率が下がる「受益者還元型信託報酬」という仕組みがあります。
【増やしつつ定期的に分配金をもらいたい方向け】
- 投資信託(4):Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)
設定日:2024年1月31日
純資産総額:159億円
基準価額:11,205円
信託報酬(税込):年0.10725%
実質コスト:0.056% ※2024年1月31日~2024年5月30日
トータルリターン(1年):7.70% ※2025年2月28日時点
シャープレシオ(1年):0.88 ※2025年2月28日時点
組入銘柄の配当利回り:4.2% ※2025年2月28日時点
分配金利回り:2.74%
分配金健全度︎:1年100%
*分配金のうちの「普通分配金」が占める割合。100%=元本取り崩しがない
日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い50銘柄に投資し、「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」の動きに連動する投資成果をめざす投資信託です。年6回、奇数月に決算を行い、分配金を支払います。NISAの成長投資枠で投資が可能となっています(つみたて投資枠は対象外)。分配金は2024年9月、12月(11月分)、2025年1月にそれぞれ100円出ていて、分配金利回りは2.74%となっています。
- 投資信託(5):日経平均高配当利回り株ファンド
設定日:2018年11月9日
純資産総額:1,797億円
基準価額:17,964円
信託報酬(税込):年0.693%
実質コスト:0.350% ※2023年12月16日~2024年6月17日
トータルリターン(5年):年20.41% ※2025年2月28日時点
シャープレシオ(5年):1.26 ※2025年2月28日時点
組入銘柄の配当利回り:4.6% ※2025年1月31日時点
分配金利回り:3.47%
分配金健全度︎:3年100% 5年85.16%
日経平均株価構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い30銘柄程度に投資をする投資信託です。年2回、6月と12月に決算を行い、分配金を支払います。アクティブファンドではあるものの信託報酬は控えめです。NISAのつみたて投資枠でも投資可能となっています。分配金は2024年6月に280円、12月に330円出ていて、分配金利回りも3.47%となっています。
よい投資信託を選ぶ5つの基準やタイプ別向いている投資信託を参考にしていただき、投資行動に活かしていただければ幸いです。
- 本記事で紹介した個別銘柄については、あくまでも参考として申し述べたものです。投資の最終決定は各自の責任でお願いいたします。
- 本ページは2025年3月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。
オススメ

頼藤 太希
経済評論家・マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。(※現在は放送終了)」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(@yorifujitaiki)
頼藤 太希のプロフィールを見る




