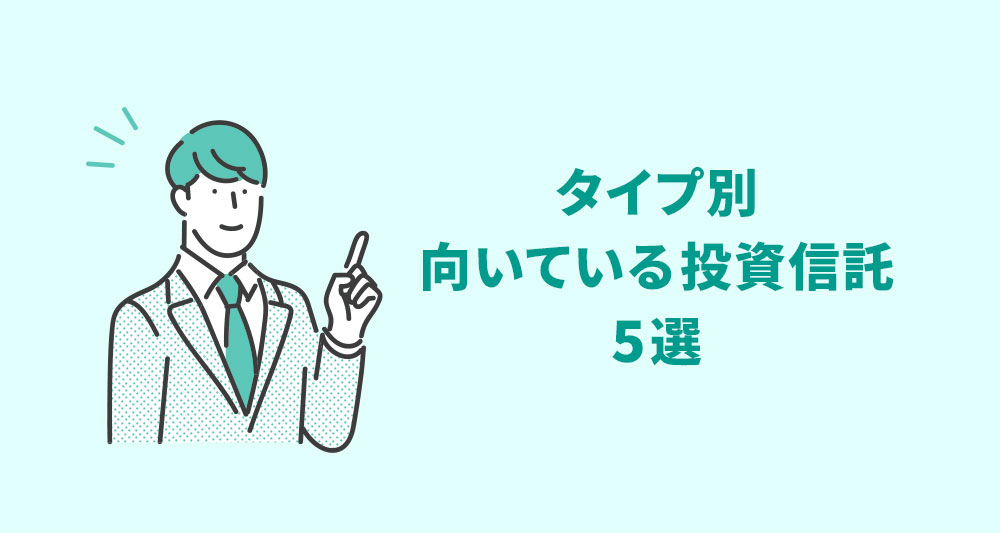


【この記事を読んでわかること】
- 高配当株とは、株価に占める配当金の割合(配当利回り)が高い銘柄。ただ、集中投資してしまうとその銘柄が値下がりしたときの損失が大きくなる
- 高配当株ファンドを利用すれば、1本で複数の高配当株にまとめて投資できる。少額から取り組めて、NISAや積立投資とも相性がよい
- 高配当株ファンドを選ぶ際には「分配金利回り」「トータルリターン」「コスト」「純資産総額」「分配金健全度」に注目
新NISAでは投資で得られた利益(値上がり益・配当金・分配金)が一生涯にわたって非課税にできることから、高配当株に人気が集まっています。ただ、高配当株に興味はあるものの、どれを選べばよいかわからないという方もいるでしょう。そんな方におすすめなのが、高配当株に手軽に分散投資できる高配当株ファンドです。
- ただし、高配当株ファンドであっても、新NISA成長投資枠では以下のファンドは対象外となるのでご注意ください。
- 信託期間が20年未満の投資信託
- 毎月分配型の投資信託
- ヘッジ以外の目的でデリバティブ取引による運用が行われている投資信託
今回は、高配当株ファンドの銘柄の選び方をご紹介します。
そもそも「高配当株」ってなに?メリットと注意点は?
配当金は、企業が株主に対して支払うお金です。企業は、得られた利益や配当の方針、今後の業績などを踏まえて配当金の金額を決め、利益の一部を株主に還元しています。株主は、保有している株数に応じて配当金を受取ることができます。
高配当株とは、株価に占める配当金の割合(配当利回り)が高い銘柄のことです。
配当利回り=年間予想配当金÷株価で算出されます。
「配当利回りがいくら以上だと高配当株」という明確な基準はありませんが、一般的には3%を超えてくると高配当だといわれます。
高配当株のメリットには、次のようなものがあります。
高配当株のメリット1:日々の株価の変動を気にする必要がない
株式投資というと、値上がりする株を買って売買差益(キャピタルゲイン)を得ることを狙うイメージがあるかもしれません。確かに、タイミングを計ってうまく売買ができれば大きく儲かる可能性がありますが、思惑に反して値下がりした場合には大きく損をしてしまうこともあります。
高配当株から受取れる配当金はインカムゲインといって、保有しているだけで受取ることができます。企業が利益を上げ続けていれば、その企業の株を持っている限り、配当金を受取り続けられる可能性が高いです。
高配当株のメリット2:配当金の再投資で複利効果が得られる
複利効果は、運用で得られた収益を投資することで、運用金額が増え、その結果リターンも増えていく効果のことです。高配当株で得られた配当金で再投資することで、より効率よくお金を増やす期待ができます。
高配当株のメリット3:新NISAと相性がいい
新NISAでは、株・投資信託・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)に投資することで得られた利益(値上がり益・配当金・分配金)が生涯にわたって非課税にできます。通常20.315%引かれる税金がゼロにできるのは大きいメリットです。
高配当株を新NISAの成長投資枠で購入して保有していれば、それだけで定期的に非課税の配当金が受取れる状態を作ることができます。
高配当株のメリット4:相場全体の下落に比較的強い
高配当株は、市場の下落にも比較的強い傾向があります。市場全体が下落しているときには、優良の高配当株であっても一時的に値下がりします。しかし、株価が下落すると配当利回りは上昇します。業績好調の高配当株ならば、割安感から買いが集まります。相場全体の下落に強く、下落からいち早く抜け出しやすい傾向にあるのです。
また、相場不調の時に配当金が受取れれば、辛抱強く回復を待ちやすいですよね。
しかし、高配当株投資には注意点があります。
それは「配当利回りの高い銘柄に飛びついてはいけない」ということです。
配当利回りの計算式は「年間予想配当金÷株価×100」ですが、配当利回りが高くなるには
- 年間予想配当金が増える
- 株価が下がる
のどちらかです。
後者の場合、業績が悪化した銘柄である可能性が高まります。
業績悪化が続くと思われる銘柄は投資家が敬遠するため、どんどん株価は低くなる傾向にあります。業績が悪いのであれば、配当金の額も減る可能性は高いでしょう。
つまり、配当利回りが高いだけで飛びついてしまうと、損をする可能性が高いというわけです。
高配当株に投資する場合には、業績は好調なのか、財務は健全なのかを必ず確認しましょう。また、そうした値下がりのリスクや減配(配当金の減額)のリスクを下げるためには、1銘柄や2銘柄に集中投資するのではなく、10銘柄から20銘柄に分散して投資することが大切です。
そこで、分散して高配当株に投資するのが面倒という方におすすめなのが「高配当株ファンド」です。高配当株ファンドとは、複数の高配当株に分散しながら投資している投資信託です。
高配当株ファンドには、次のようなメリットがあります。
高配当株ファンドを活用するメリット1:分散投資が手軽にできる
高配当株ファンドは1本買うだけで複数銘柄に分散投資できます。仮に組み入れられている銘柄のどれかの業績が悪化し、減配や無配になったとしても、他の銘柄からの配当などでカバーすることが期待ができます。投資信託の運用会社は、銘柄を吟味してときどき入れ替え(ポートフォリオの見直し)を行いますので、手間もかかりません。
高配当株ファンドを活用するメリット2:積立・再投資がしやすい
株も近頃は1株から購入できるようになってきました。しかし、購入金額は株価によって変わるので銘柄ごとにまちまちです。「1万円ちょうど」などと一定金額で積立投資することができません。
その点、投資信託ならば金融機関によっては100円と少額から1円単位で積立投資ができます。毎月いつ、どの商品を、いくら積み立てるかを設定すれば、あとは自動的に投資が進みます。投資信託から得られる分配金も、設定すれば自動的に再投資できるので、複利効果も得やすくなっています。
高配当株ファンドを選ぶ5つのポイント
高配当株ファンドを選ぶポイントは、次の5つです。
①分配金利回りの推移…5年、10年と安定して高く、他のファンドよりも高いか
②トータルリターンの推移…5年、10年と安定してプラスで、他のファンドよりも高いか
③低コストであるか(信託報酬・実質コスト)
④純資産総額50億円以上か(設定後1年未満は除く)
⑤分配金健全度が100%(または高い)か
分配金利回りやトータルリターンは、あくまで過去の実績であって、将来も高い保証はありません。しかし、過去5年、10年ときちんとした運用を行い、実績がある高配当株ファンドの方が信頼できるでしょう。
そのうえで、低コストのファンドを選ぶことをおすすめします。保有中のコストである信託報酬の安い投資信託であれば、利益が出しやすくなります。また、信託報酬だけでなく実質コストも確認しましょう。実質コストは、投資家が実際に負担した手数料のことです。前もっていくらと示せないため、ファンドの一定期間の運用結果をまとめた「運用報告書」に記載されています。「信託報酬が安いからと購入したにもかかわらず、実際には実質コストが高かった…」ということもありえますので、チェックしておきましょう。
なお、設定後間もないファンドで、運用報告書がまだ出ていない場合などは、確認できません。
投資信託の運用には、ある程度の資産が必要です。純資産総額は、新規の投資信託を除き少なくとも50億円は欲しいところです。純資産総額が少ないと分散投資がしにくいですし、早期に運用を終了する繰り上げ償還が行われる可能性もあります。
分配金健全度は「分配金に占める普通分配金の割合」を示したものです。
分配金には、運用の成果から支払われる「普通分配金」と、元本の一部を取り崩して支払われる「特別分配金(元本払戻金)」があります。「運用がうまくいっていないのに分配金を出さなければならない」という場合、投資信託は元本を取り崩して分配金を支払います。しかし、特別分配金は投資家の利益ではなく、単にお金が戻ってきただけです。
分配金を支払う投資信託の場合は、分配金健全度が100%(=特別分配金がない)、または100%ではなくても高いことが望ましいでしょう。
- ここで説明している「分配金健全度」とは計算日と一定の基準日との比較において、分配金における普通分配金の割合を示した指標であり、個々のお客さまについての普通分配金の割合を示したものではありません。
お金のプロが選ぶ高配当株ファンド3選
イオン銀行を通じてマネックス証券で購入可能な高配当株ファンドのなかから3つ紹介します。なお、以下のデータは断りのない限り2024年12月5日時点のものです。
①Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)
設定日:2024年1月31日
純資産総額:113億円
基準価額:10,798円
信託報酬(税込):年0.10725%
実質コスト:0.056% ※2024年1月31日~2024年5月30日
騰落率(設定来):8.64% ※2024年11月29日時点
組入銘柄の配当利回り:4.2% ※2024年10月31日時点
分配金利回り(1年):0.93%
分配金健全度:--
日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い50銘柄に投資。「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」の動きに連動する投資成果をめざす投資信託です。年6回、奇数月の30日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金を支払います。年金を受取っている人が利用すると、奇数月は分配金、偶数月は年金と、毎月収入のある状態を作ることができます。
分配金は2024年9月30日と12月2日にそれぞれ100円出ており、分配金利回りは0.93%となっています。分配金健全度の実態はこれから判明するので気になるところです。
②(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株
設定日:2024年6月28日
純資産総額:19億円
基準価額:9,913円
信託報酬(税込):年 0.165%
実質コスト:--
騰落率(設定来):0.45% ※2024年11月29日時点
参照指数の配当利回り:3.64% ※2024年11月29日時点
分配金利回り(1年):0.80%
分配金健全度:--
世界各国の株式に投資することで、先進国23か国と新興国24か国の株式の中から配当利回りの高い銘柄が抽出された「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス」の動きに連動する投資成果をめざす投資信託です。月次レポート(2024年10月)によると、組入銘柄数は483銘柄と、さまざまな銘柄に分散していることがわかります。毎年2月・5月・8月・11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に分配金を支払います。
2024年6月28日に運用を開始した、まだ新しい商品です。分配金は2024年11月20日に80円出ており、分配金利回りは0.80%となっています。こちらも、分配金健全度の実態はこれから判明します。
③日経平均高配当利回り株ファンド
設定日:2018年11月9日
純資産総額:1,641億円
基準価額:17,338円
信託報酬(税込):年0.693%
実質コスト:0.350% ※2023年12月16日~2024年6月17日
騰落率:(5年)98.82% (設定来・年率)16.18% ※2024年11月29日時点
組入銘柄の配当利回り:4.5% ※2024年10月31日時点
分配金利回り(1年):3.19%
分配金健全度:(3年)100% (5年)81.95%
日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い30銘柄程度に投資をすることで、配当と中長期的な値上がり益を得ることを目指す投資信託です。年2回、6月・12月の15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配金を支払います。アクティブファンドながら信託報酬は控えめ。NISAのつみたて投資枠でも投資することができます。
分配金は2023年6月15日に330円、12月15日に270円、2024年6月17日に280円と安定して出ており、分配金利回りも3.19%と高くなっています。分配金健全度は5年で81.95%ですので、特別分配金も多少出してはいますが、定期的に分配金が欲しい方ならば利用価値のある商品といえます。
高配当株ファンドを利用すれば、複数の高配当株にまとめて投資でき、高い配当金の恩恵を受けることができます。NISAで投資すれば、分配金も非課税で受取ることができます。
ご紹介したファンドを参考にしていただき、投資行動に活かしていただければ幸いです。
- 本記事で紹介した個別銘柄については、あくまでも参考として申し述べたものです。投資の最終決定は各自の責任でお願いいたします。
- 本ページは2024年12月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
お申込みに際しては、以下の留意点を必ずご確認ください。
オススメ

頼藤 太希
マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
頼藤 太希のプロフィールを見る




