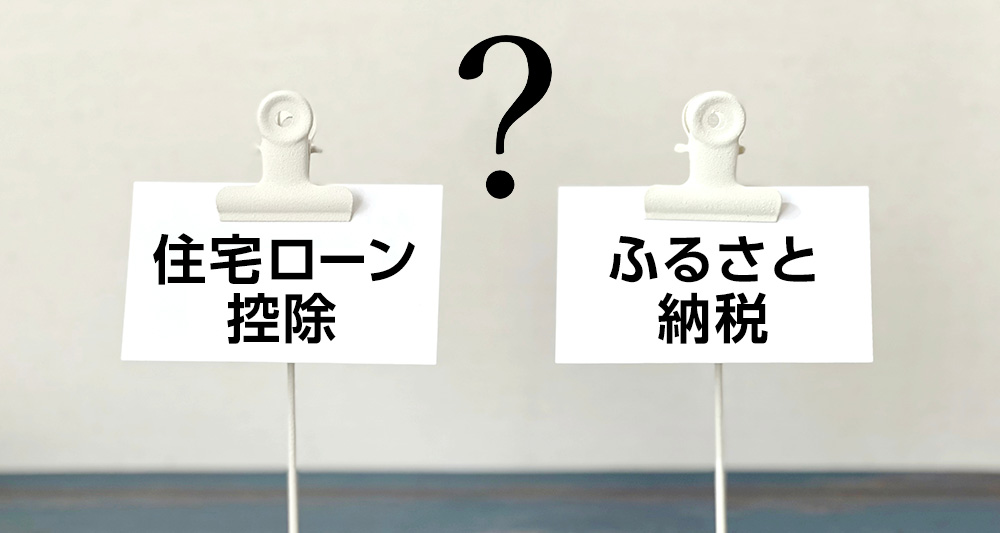なぜ住宅ローン控除に確定申告が必要なのか?
住宅ローン控除とは前述の通り、所得税と住民税が控除対象となります。年末時点でのローン残高の1%が納めた所得税から還付され、所得税から還付しきれなかった分に関しては、住民税から還付されます。個人事業主に関しては毎年自分自身で確定申告を行うため、特に意識する必要はありませんが、会社員の場合は違います。通常の場合、過不足の調整や所得税の確定は年末調整によって行いますので、特別なことが無い限りは確定申告の必要がありません。しかし、住宅ローン控除のような税額控除を受けるためには、年末調整手続きではなく、確定申告でなければならないため、会社員であっても自分で確定申告をする必要があるのです。
確定申告に必要な書類
会社員が確定申告を行う場合に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 住民票
- 住宅ローンの借入金残高証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 売買契約書または建築請負契約書
1. 確定申告書
会社員の場合必要な申告書は「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の二種類です。この申告書類は、税務署で入手できる他、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷しても構いませんし、国税庁が用意した専用サイト(e-TAX)を利用する場合には印刷は必要ありません。
2. 源泉徴収票
年末調整に伴って会社から必ず渡されます。
3. 住民票
市区町村役場で発行してもらいます。
4. 住宅ローンの借入金残高証明書
ローンを組んだ金融機関から通常送られてきます。
5. 土地・建物の登記簿謄本
登記を担当の司法書士に取得の依頼をするか、管轄の法務局で取得することもできます。
6. 売買契約書または建築請負契約書
住宅購入の際に業者から必ずもらうものです。
以上を漏れなく揃えるようにしましょう。
確定申告の手続き
上記の書類が揃ったらいよいよ記入、手続きとなります。まず手続きを行う場所ですが、管轄する税務署で手続きを行います。税務署に直接行く以外には、郵送する方法と、e-TAXで入力、電子申請を行う、といった方法も用意されています。自分の都合にあった方法を選択しましょう。
手続きを行う時期は、原則として毎年2月16日~3月15日です。いずれかが土日にかかる場合には、直近の月曜日に期日が調整されます。
記入する書類は上記の必要書類「1. 確定申告書」の
- 確定申告書A
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
の2枚です。
この2枚へ上記の必要書類2.~6.より情報を探して記入していきます。
国税庁のホームページには確定申告書の記入の手引きや見本が記載されていますので、それを参考に記入するとよいでしょう。必要な情報を全て記入し、必要な数字を算出したら、あとは提出するのみです。
2年目以降はどうなる?
1年目に上記の通り確定申告を完了させれば、2年目以降の申告は不要です。2年目の10月下旬頃、税務署からは「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」が、ローンを組んだ金融機関からは「残高証明書」が送られてきます。「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」に必要事項を記入し、「残高証明書」と共に会社に提出するのみでOKです。あとは年末調整に住宅ローン控除が加味され、自動的に差引が行われます。
1つ注意したいのは、必要書類の扱いについてです。「残高証明書」は毎年送られてきますが、「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」は、2年目の10月に今後9年分が一括して送られてきます。控除期間中は毎年使うものですので、紛失しない様大切に保管しましょう。
夫婦でローン組み&共有の場合の注意点
住宅購入に際し、共有名義にして、持ち分に応じてローンを組む方法の場合注意が必要です。例えば、共働きで持ち分に応じてローンを支払っていた妻が退職し、専業主婦になった場合、妻分の所得税が発生しなくなります。そのため、ローン控除の計算はなりたたず、税金還付の恩恵は受けられなくなります。また、収入のない妻分の支払いを夫の収入のうちから返済する場合、肩代わりの額次第では贈与とみなされ、贈与税を支払う場合もありますので、気をつけましょう。当然、妻分のローンを支払うからといって、夫分のローン残高が加算されることはありません。
このように、夫婦共有名義でそれぞれ住宅ローンを組む場合、将来の生活設計を考慮することがとても重要になります。
今回のまとめ
- 住宅ローン控除のような税額控除を受けるためには確定申告を行わなければならない
- 会社員の方でも1年目の控除には確定申告が必要
- 2年目以降は「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と「残高証明書」を会社へ提出
- 夫婦の共有名義でローンを組む場合は、将来の生活設計も見据えることが重要である
- 本ページは2018年11月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
関連情報
現在の年収やお家賃から、お借入れ可能額を試算してみましょう。
インターネットで住宅ローン事前審査のお申込みが可能です。
オススメ

江田 英明
マネーコンサルタント
ファイナンシャルプランナー。資産形成・資産運用に関するコンサルティングを中心に、金融相談や記事の執筆を手掛けており、Webライター・編集者としても活動中。コストパフォーマンスをとことん突き詰める主義で、おトク情報の収拾に余念がない節約派。
江田 英明のプロフィールを見る