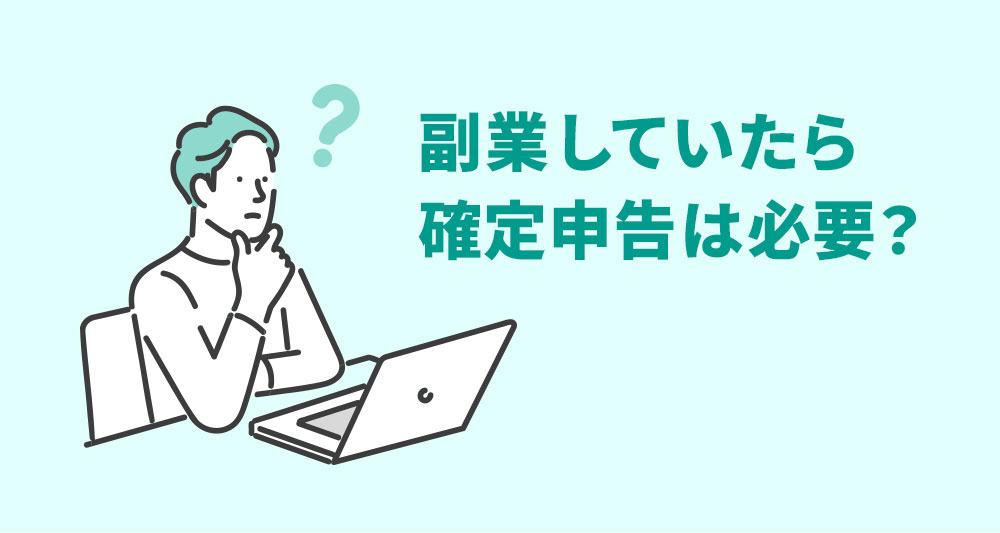
扶養から外れるとどうなる?外れているのに放置した場合のデメリットは?


気になる記事はお使いのデバイスでブックマーク登録できます
【この記事を読んでわかること】
- 年収が「年収の壁」を超えると、扶養から外れて、新たに税金や社会保険料の負担が生じる
- 扶養から外れているのに放置すると、税金や社会保険料をさかのぼって支払う必要がある
- 扶養から外れているにもかかわらず、外れる前の健康保険証を使ってしまうと、本来負担しなくて済むはずの医療費7割分を負担しなくてはならなくなる
パート・アルバイトなどをしていて、配偶者や親などの扶養に入っている方はたくさんいます。しかし、年収が一定の「年収の壁」を超えると、扶養から外れることになります。今回は、扶養から外れるとどうなるのかをご紹介します。また、扶養から外れているのにそのまま放置した場合にどんなデメリットが生じるのかを解説します。
扶養は税法上と社会保険上の2種類ある
扶養とは、自分で稼いだお金だけでは生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助をすることです。「夫(妻)が妻(夫)を扶養する」とは、「夫(妻)が妻(夫)を養う」ということです。夫婦だけでなく、子どもや両親などの援助をすることも扶養です。以降、扶養する方のことを「扶養者」、扶養される方のことを「被扶養者」と呼ぶことにします。
2024年から2025年にかけて「年収の壁」が大きな話題になりました。年収の壁とは、「年収がこの壁を超えると税金や社会保険料の負担が増える」というボーダーラインのことです。被扶養者は年収を年収の壁以内に収めれば、税金や社会保険料を負担する必要がありません。しかし年収が年収の壁を超えると、被扶養者は扶養から外れ、新たに自分で税金や社会保険料を負担する必要が出てきます。
≫関連コラム
年収の壁どうなった?扶養範囲内で働く場合の年収はいくらまで?
扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。
税法上の扶養から外れると、被扶養者は自分で所得税や住民税を納める必要が出てくるほか、扶養者の所得税や住民税が高くなることもあります。社会保険上の扶養から外れると、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要が出てきます。
年収の壁は複数あり、被扶養者がどの壁を超えたか(超えなかったか)によって、かかる税金・社会保険料が変わります。ここでは、2025年時点の主な年収の壁と税金・社会保険料のどちらに影響があるかを簡単に紹介します。
主な年収の壁
- 100万円の壁…住民税がかかる【税金】
- 106万円の壁…社会保険料がかかる(対象者のみ)【社会保険料】
- 123万円の壁…所得税がかかる【税金】
- 130万円の壁…社会保険料がかかる【社会保険料】
- 150万円の壁…特定親族特別控除が減りはじめる【税金】
- 160万円の壁…配偶者特別控除が減りはじめる【税金】
- 188万円の壁…特定親族特別控除がなくなる【税金】
- 201.6万円の壁…配偶者特別控除がなくなる【税金】
被扶養者の年収がこれらの壁を超えると、被扶養者は自分で税金や社会保険料を納めることになるため、負担が増えます。また、配偶者を養う扶養者が受けられる配偶者控除や配偶者特別控除・大学生年代の子を養う扶養者が受けられる特定親族特別控除が減ったりなくなったりすると、扶養者の税金が増えることにつながります。
扶養の範囲を超えて働いているのを放置するとどうなる?
パート・アルバイトで働く方のなかには、税金や社会保険料の支払いを防ぐために、年収の壁を超えないような働き方をしている方がいます。特に、社会保険料がかかる130万円の壁(人によっては106万円の壁)を超えないように働いているケースは多くあります。
社会保険上の扶養のメリットは、自分で国民年金の保険料を払わなくても、年金制度に加入している扱いになることです。扶養者の厚生年金保険料も変わらないのですが、被扶養者は将来国民年金がもらえます。また被扶養者は自分で健康保険に加入する必要もなく、扶養者の保険を利用できます。これによって扶養者の保険料が増えるわけでもないので、とてもおトクです。もし社会保険上の扶養の壁を超えると、支払う必要がある社会保険料はおおよそ年間で15万円以上と高額ですから、壁を超えずに働こうとするのです。
しかし、なかには被扶養者が扶養の範囲を超えて働いているにもかかわらず、そのことを扶養者に伝えずに放置しているケースもあります。「うっかり超えてしまった、どうしよう」と悩んだ挙句に隠してしまう場合もあれば、そもそも超えたことに気づかない場合もあります。2カ所以上で掛け持ちして働いていて、合計がいくらかわかっていなかったという場合もあります。
たとえば、被扶養者(扶養者の配偶者)が年収の壁を超えて働いていたことを、扶養者に伝えていなかったとします。本来は税法上の扶養も社会保険上の扶養も受けられない年収だったにもかかわらず、扶養者は税法上の扶養も社会保険上の扶養も受けられる形で年末調整を済ませていたという場合、次のことが起こります。
扶養者の税金が増える
扶養者は、勤め先で年末調整をするときに「配偶者を扶養している」と申告しているため、配偶者控除(または配偶者特別控除)によって所得税や住民税が軽くなっています。しかし、実際は税法上の扶養を受けられないのですから、この申告は誤っていたことになります。
被扶養者も勤め先で年末調整をしていますので、税務署は「扶養者と被扶養者で申告している年収が違う」とわかります。今回は、実際には扶養者の申告額が少なかったので、扶養者の勤め先に「扶養控除等の見直し」という通知が届きます。
扶養控除等の見直しは、「年末調整で配偶者控除や扶養控除に間違いがありそうなので確認してください」という通知です。勤め先はこの通知を受取ったら、従業員(ここでは、扶養者)に確認を行います。これにより扶養から外れていることが分かった場合、税金の再計算が行われ、不足分を追加納税することになります。多くの場合、勤め先が追加の税金を納付し、翌月の給与などから追加で支払った税額を差引きます。
≫関連コラム
「忘れると31万円の損」年末調整でするべき6つの控除
社会保険の扶養からも外れる
被扶養者の年収が130万円(条件を満たせば106万円)を超えていれば、社会保険上の扶養から外れ、自分で社会保険料を納める必要があります。しかし、扶養者の勤め先で扶養から外れる手続きをしていなかった場合は、さかのぼって扶養から外れます。いつまでさかのぼり、いつから外れるかは組合(運営団体)の判断になります。
被扶養者の扶養から外れていた期間は下記の2択となります。
- パート先で社会保険に加入する
- 国民健康保険と国民年金に加入する
人によりどちらになるかが異なりますが、いずれにせよ未納分の保険料を追加で納めなくてはなりません。本来なら支払っているはずの保険料ですが、未納になっている期間が長くなればなるほど追加で納めなくてはならない保険料も多くなるのですから、家計へのダメージとなることは間違いありません。
扶養者からの保険証を使っていたら返金も
病院や薬局で保険証を提示すると、基本的に医療費の3割を負担することで治療や処方が受けられます。これは、残りの7割を加入している健康保険組合が負担してくれているからです。
しかし、本来は扶養者に扶養されていない時期に被扶養者が扶養者の保険証を使っていたとしたら、その期間の医療費の7割分を自ら負担しなくてはなりません。この7割分は加入しなおした健康保険(国民健康保険)は負担してくれませんので、自己負担がさらに増えてしまいます。
国民年金保険料も支払う必要あり!
社会保険上の扶養に入っていれば、国民年金の「第3号被保険者」となります。国民年金の第3号被保険者は、国民年金保険料を支払う必要がありません。しかし実際は、社会保険上の扶養には入っていなかったのですから、国民年金の「第1号被保険者」となります。そのため、第1号被保険者だった期間の国民年金保険料も支払う必要があります。国民年金保険料は毎年前後します。2025年度は月17,510円です。仮に2025年度の1年分をさかのぼって支払うとなれば、17,510円×12カ月=21万120円を支払わなければならなくなります。
申請はもれなく行おう
もしかしたら、被扶養者が扶養者に正しい年収を伝えなかったのは、「多少違っていても大丈夫だろう」という気持ちからだったかもしれませんが、そんなことはありません。後になって困ることのないように、正しくもれなく申請しましょう。
- 本ページは2025年4月時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。また、今後予告なしに変更されることがあります。
- 2025年12月2日以降は、健康保険証は本人確認書類として利用できなくなりますので、ご留意ください。
お申込みに際しては、以下のご留意点を必ずご確認ください。
オススメ

高山 一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)
(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。X(旧Twitter)→@takayamakazue
高山 一恵のプロフィールを見る






